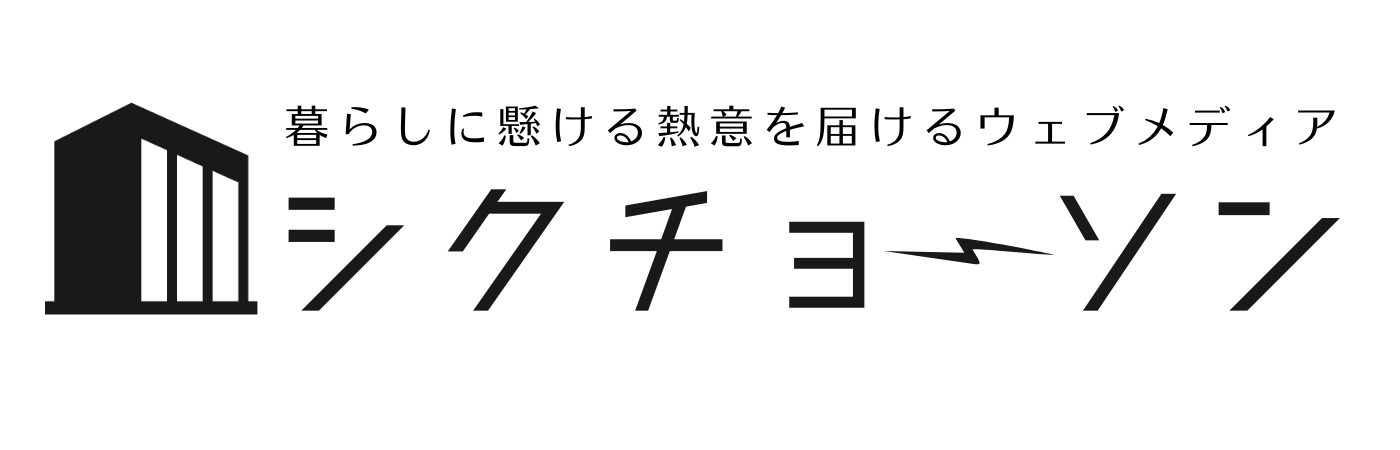日本漢字能力検定協会は12月19日、青山学院大学 総合プロジェクト研究所「学習科学青山研究所」と共同研究を開始した。
学習科学青山研究所は、AI技術や一人一台情報端末を建設的に活用して一人ひとりの学ぶ力を引き出す学習環境デザインの開発と社会実装を目指し設立された。同協会は、飛躍的に進歩する文章生成AIサービス等の情報通信技術を使いこなす視点に立ち、学習基盤である言語能力の育成を支援する環境の開発と実装を目指す「未来のリテラシー教育デザイン部門」において、共同研究に取り組む。
生成AIの登場で変わりつつある教育現場
規模言語モデル(LLM)による生成AIの登場など著しい進展が見られる中、改めて「我々、人間の賢さがどこにあるのか」が話題になっている。学校教育においても、子どもたちの資質・能力を育む授業や学習評価のすがた、民間教育サービスの在り方など、従来のやり方から最新の情報通信技術を活用した学習環境へとデザインし直す必要性が高まっている。
未来のリテラシー教育デザイン部門では、「人はいかに学ぶか」を実証的に研究する学習科学の知見に基づき、デジタル学習基盤の一翼である言語能力の在り方の検討として、「生成AIツールを活用した言語能力の育成と評価に関する実証研究」を開始している。
今後は、自分の考えを他者に伝わるように言語表現を吟味し磨くプロセスでのAI活用を通して、利用対象者である児童・生徒自身が自らの言語理解を深めていく学習を支援するシステムの開発を目指す。また、本システム活用に興味をもった実証実践校を対象に試用してもらい、効果検証を進める。
共同研究の途中経過や研究成果は、今後、同協会ホームページで公開予定だという。
ドリル教材とは異なるアプローチ方法を検討
本発表にともない、学習科学青山研究所および日本漢字能力検定協会それぞれからコメントが掲載されている。
学習科学青山研究所 所長 益川弘如氏
学習科学青山研究所(Aoyama Institute for the Learning Sciences; 略称AILS)では、一人ひとりなりの「学ぶ力」を引き出し、高め、磨いていくような「学習環境のデザイン」を構築する認知科学・学習科学研究を推進し、情報通信技術が発達し続ける現在の社会において、「人はどこまで賢くなることができるのか」の問いに応え得る未来の学習環境を追求しています。このたびの共同研究では、認知科学・学習科学の研究知見を生かして、これからの社会を担う学び手を支えていくような、学習プラットフォームの開発と実験的・実践的検証、社会実装を進めていきます。
公益財団法人 日本漢字能力検定協会 客員研究員 安井理紗氏
漢字の指導では、書いて覚えるドリル教材が多くの教育現場で取り入れられています。一方で、漢字の小テストなどの演習問題を解くことができても、作文など日頃の言語活動で学習した語を上手く使いこなせていないように感じるとのお声を学校関係者の方々からいただくことがあります。本研究所では、ドリル教材とは異なるアプローチ方法を検討し、「ことばの運用場面」を通して漢字・日本語の能力を育み評価する方法について検討して参ります。