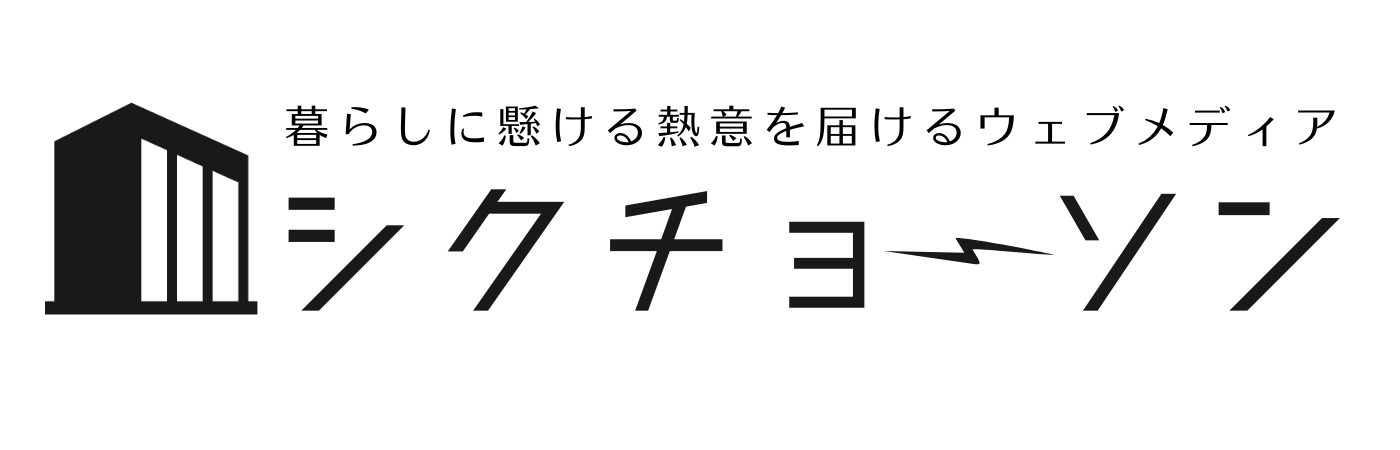三重県多気町において、住民同士が協力し合う新しい交通システム「共助型ライドシェアサービス」の実証実験が行われた。実施主体は三重広域連携スーパーシティ推進協議会で、一般社団法人ふるさと屋、一般社団法人日本自動車工業会(自工会)などの協力のもと、地域課題の解決を目的とした取り組みの一環として実施された。
交通弱者の声を背景に、新しい移動モデルを検証
実証地域である多気町は中山間地域であり、公共交通が十分に整備されていない。そのため、自家用車に依存せざるを得ない住民が多く、高齢者や子育て世代を中心に移動に関する課題が浮き彫りになっている。
実証実験の背景として、住民ヒアリングでは「運転免許を返納してから外出を控えるようになった」「子どもの送迎で自分の時間が取れない」といった声が上がっていた。こうした状況を受け、共助型ライドシェアが有効な選択肢になり得るかを検証することが本実験の目的だ。
MSP構想を活用した安全性と信頼性の担保
実証実験では、自工会が提唱する「Mobility Smart Passport(MSP)構想」を導入。共助ドライバーには、MSPアプリと検証可能なデジタル証明書(VC)を通じて、地域住民であることの証明が求められた。さらに、ドラレコデータを用いた走行履歴から安全運転スコアを算出し、信頼性と安心感を確保した形でサービスを提供した。
実証の成果と住民の反応
2025年3月10日から21日の期間に、多気町・松阪市・大台町を運行エリアとしてサービスを実施。住民からは、移動の自由が広がったことへの喜びに加え、「共助型という仕組みにより住民同士の交流が生まれた」との声も聞かれた。アンケート結果からは、ドライバー・利用者双方の満足度が高く、地域活性化につながる副次的効果も確認された。
地域・関係者からのコメント
三重県多気町の久保行央町長は「地域のつながる力を活かした新たな交通モデルの可能性を実感した」と語り、一般社団法人ふるさと屋の中西眞喜子代表も「住民主体の助け合いが、街の活性化につながった」と振り返る。また、自工会の山下義行氏は「誰もが自由に移動できる社会を実現するため、MSP構想をさらに推進していく」と意気込みを示した。
官民連携による広域的な地域課題解決モデル
本実証は、三重広域連携スーパーシティ推進協議会のモビリティ分科会が主導。協議会は多気町を含む6町と30の民間企業が連携し、AIやビッグデータといった先端技術を活用して、高齢化・過疎化など地域課題の解決を目指している。今回のライドシェア実証もその一環であり、今後の持続可能な地域交通のモデルケースとして注目される。
「誰もが、好きなときに、好きなところへ」移動できる社会の実現に向け、三重からの新たな挑戦が始まっている。