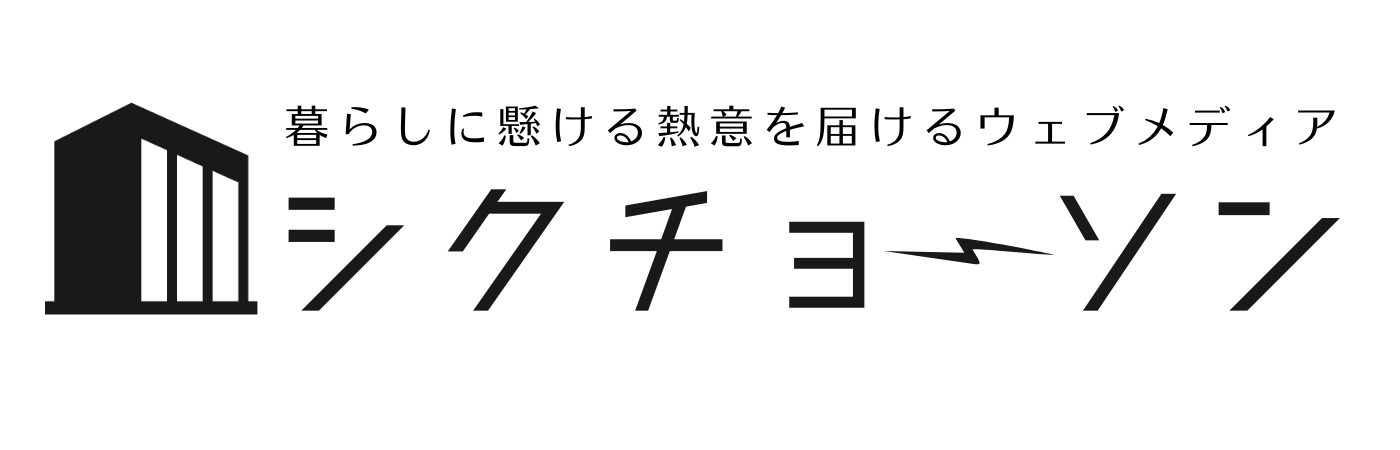リユース市場が静かに、しかし確実に拡大している。背景には、フリマアプリの普及や環境意識の高まりに加え、「不要品を手間なく手放したい」という生活者のニーズがある。
そんな中、全国の自治体と連携しながらサービスを展開するのが、株式会社マーケットエンタープライズが提供するリユースプラットフォーム「おいくら」だ。
導入自治体は250を超え、人口カバー率は40%以上──なぜ今「おいくら」が社会に広がっているのか、その理由と未来をひもとく。
リユースは“次の当たり前”へ──3兆円市場のいま
リユース市場が活況なのは、ここ数年、コロナ禍による断捨離需要やライフスタイルの変化を受けて、自宅の整理やモノの見直しを進める人が増えたことが大きい。また、物価高など社会情勢を受け、“新品には手を出しづらい”と考える人が増えつつあることも理由のひとつだろう。
実際、リユース市場全体の規模は拡大傾向にある。環境省の調査では、2022年時点で国内のリユース市場は約3兆円規模に達しており、今後も成長が見込まれている。
参考:環境省 リユース市場規模調査等(※pdf)
一方で、環境省が行ったリユース市場規模調査では、リユースを過去1年間では利用したことはないと回答した人が増加傾向にあるというデータも出ている。株式会社マーケットエンタープライズ おいくらカンパニー カンパニー長の池﨑敬氏は、次のように語る。
「リユース市場は拡大していますが、リユース体験者はまだ少ないのが現状です。この相反する結果は、リユースを積極的に繰り返し利用する層と体験したことのない層の二極化が進んでいることの現れだと捉えています。
最近では、高齢者の方が“初めてのリユース体験”として『おいくら』を利用するケースが増えてきました。出張買取など、手間をかけずに処分できる仕組みがあることで、これまで利用機会のなかった層にも広がりが出てきていると感じています」
かつては“使い終わったモノは捨てるもの”だった。しかし今では、“次に活かす”という選択がごく自然に語られる時代が到来しつつある。
その変化の最前線にあるのが、リユースマッチングプラットフォーム「おいくら」だ。
“リユース”をもっと簡単にした──「おいくら」の仕組み
リユース市場の広がりの中でも、「おいくら」が注目される理由のひとつは、その仕組みの“手軽さ”にある。
「おいくら」は、ユーザーが売りたいモノの情報を入力すると、複数のリユースショップが査定を行い、ユーザーにとって都合の良い業者を選んで取引できるリユースプラットフォームだ。利用者にとっては、店舗をひとつひとつ回ったり、相見積もりを取ったりする必要がなく、さらには一度に15点まで見積もりが依頼できるなど、手間を最小限に抑えられる。
とくに「大型の家具・家電」に強い点が特長で、自宅からの搬出や梱包が難しく処分に困りがちなアイテムでも、出張買取によって自宅の中まで入ってスムーズに引き取ってもらえる。これは高齢者や単身世帯、引越しのタイミングなどで重宝されるポイントだ。
「我々の強みは“ライフイベントに寄り添えるリユース”です。引越し、遺品整理、子どもの独立など人生の節目に住環境の見直しをする際の“モノを手放す”場面に合わせて使っていただくケースが多くあります」(池﨑氏)


利用者からは、「高く売れること」だけでなく「すぐ来てくれる」「安心して任せられる」といった、安全かつスピード感のある体験価値への需要も高まった。一般に、モノを売る際、高く買い取ってくれる事業者を選定することが常ではある。ただし、引っ越しによる退去日など期限がある場面では、「期限内に買い取ってくれる事業者を見つけたい」というニーズも存在している。利用者のニーズは「少しでも高く売りたい」というものだけではない。利用者が重視するポイントに合わせて、自身にとって都合の良い事業者を選択し、売却先を決めることができる。
実際、同社が実施したアンケートでは、8割以上が「おいくらを利用して売却できた」と回答しており、満足度の高いサービスとして定着しつつある。また、売却できた人だけでなく、売却できなかった人からも、「今後はリユースを積極的に活用したい」という前向きな声が挙がった。
“高く売る”から“ストレスなく手放す”へ。そうした価値観の変化に対応し、より多くの人にとって使いやすいリユースの仕組みを届けているのが、「おいくら」という存在なのだ。
行政の悩みに民間が応える──全国250超の自治体で導入が進む背景
「おいくら」が広がっているのは、民間のユーザーだけではない。2025年4月現在、全国で253の自治体と連携しており、人口カバー率は41%に達している。これは、全国の約4割の住民が、何らかの形で「おいくら」の行政連携サービスにアクセスできることを意味している。

参考リンク
佐賀県小城市が引越しでごみ増加の3月より不要品リユース事業で「おいくら」と連携を開始〜「おいくら」連携自治体は250に 人口カバー率は41%を突破〜
自治体との取り組みが始まった背景には、家電リサイクル法や粗大ごみの処分にまつわる課題があった。
たとえば自治体に「テレビを捨てたい」と相談があっても、家電リサイクル法対象品目に該当するため、引き取りができない。あるいは、「使えるのに捨てるしかない」という住民の声に対し、解決手段を持たないという現場のジレンマも少なくなかった。
「そうしたときに『おいくら』はリユースのひとつの手段として紹介でき、リユースを促進するための価値提供ができます」と池﨑氏は語る。
導入のハードルが低いことも、自治体にとってのメリットだ。「おいくら」の導入にあたり、住民への広報や問い合わせにご対応いただく必要はあるものの、初期費用・ランニングコストともに“ゼロ” で導入することができる。
また、「ごみの減量」にとどまらず、「リユースを体験する住民を増やす」啓発の一環としても活用されている。とくに高齢者層にとって、出張買取という形での初めてのリユース体験は、環境意識の醸成と生活支援の両面を兼ねる存在だ。
自治体にとっては、「住民の“不”」を解決する手段として。住民にとっては、“使わなくなったモノ”を次に活かす選択肢として――。「おいくら」は、民間と行政のあいだにある“すき間”を埋める、新たなインフラとして機能し始めている。
これは余談的な要素ではあるが、利用者と「おいくら」加盟店の間に入って、トラブル解消したり、不明点に回答するなど、カスタマーサポート的機能も提供している。この理由について「とくに初めてリユースを利用する方に対して、初めの一歩はとても重要です。リユース活動の促進のためにも、我々ができる限り支援しています」と池﨑氏は説明した。
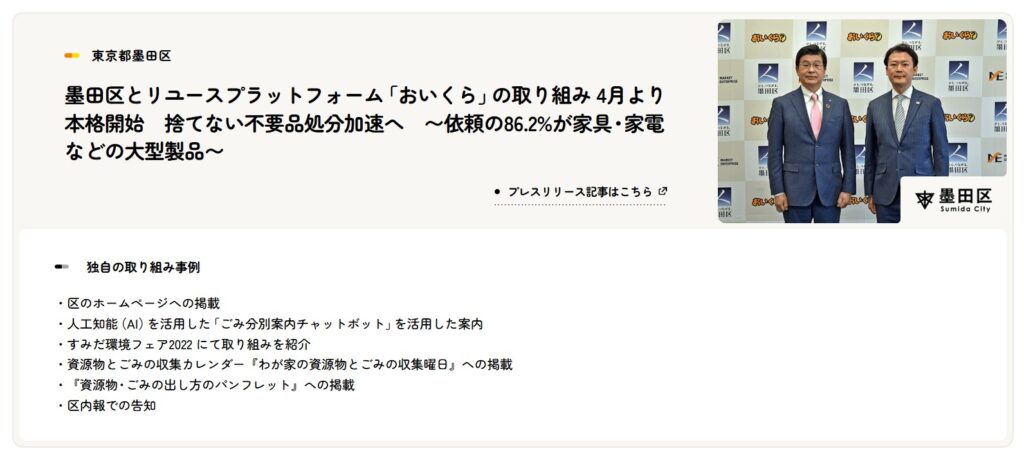
リユースから社会課題へ──マーケットエンタープライズの描く循環モデル
「おいくら」が単なる“便利な買取サービス”にとどまらないのは、その先に明確なビジョンがあるからだ。
マーケットエンタープライズが掲げるのは、「持続可能な社会の実現」。単に“モノを売る・買う”を超えて、持続可能な社会の実現のために必要な社会課題を解決することを目指している。
たとえば、中古農機具の再流通など、「おいくら」との連携をきっかけにした他分野との掛け算が進みつつある。単なる“業界の拡張”ではなく、「リユースを起点とした課題解決モデル」として構想されているのが特徴だ。
今後のリユース界隈について、5年後や10年後はどうなっていくと考えているのかを池﨑氏に聞くと次のように話してくれた。
「あくまでも私見ですが、リユースがさらに一般化することで、いずれは再販されることを前提とした製品設計や、モノの流通履歴を記録できるような仕組み(例:商品のナンバリング)も当たり前の世界がやってくるかもしれません。さらには、流通されて長く使用されればされるほど、利用者に何かしらのメリットが発生するような取り組みも広がっていくかもしれませんね。
持続可能な社会を実現させるためには、リユース市場の成長が鍵を握っていると言っても過言ではないでしょう」(池﨑氏)
同社が見据えるのは、“一事業完結型や一社完結型”ではなく、“社会全体の最適化”だ。それはまるで、「社会課題を解決するための商社」のような姿でもある。
すでに一定の広がりを見せている「おいくら」だが、真価を問われるはむしろこれから。人口減少、高齢化、廃棄物処理、福祉、そして環境。これらのテーマに共通して求められる“循環”の仕組みを、民間主導でどう形にしていくのか。
いま、「おいくら」が担っているのは、単なるリユースプラットフォームの枠を超えた、社会の“暮らしのインフラ”としての役割だ。
不要品の処分を通じて人と人、行政と民間をつなぎ、リユースという選択肢を当たり前にする。そんな未来が実現すれば、「おいくら」が築いている循環型社会のモデルは、きっと私たちの生活そのものを支える存在になっていくだろう。

池﨑敬
株式会社マーケットエンタープライズ
おいくらカンパニー カンパニー長
会計・税務システムのソフトウェア会社にて営業職に従事。
その後、大手不動産プラットフォーム事業を展開する企業で営業職、サービス設計、事業戦略立案、組織・事業マネジメントを経験。
現在は、マーケットエンタープライズにてリユースプラットフォーム「おいくら」の責任者を務める。