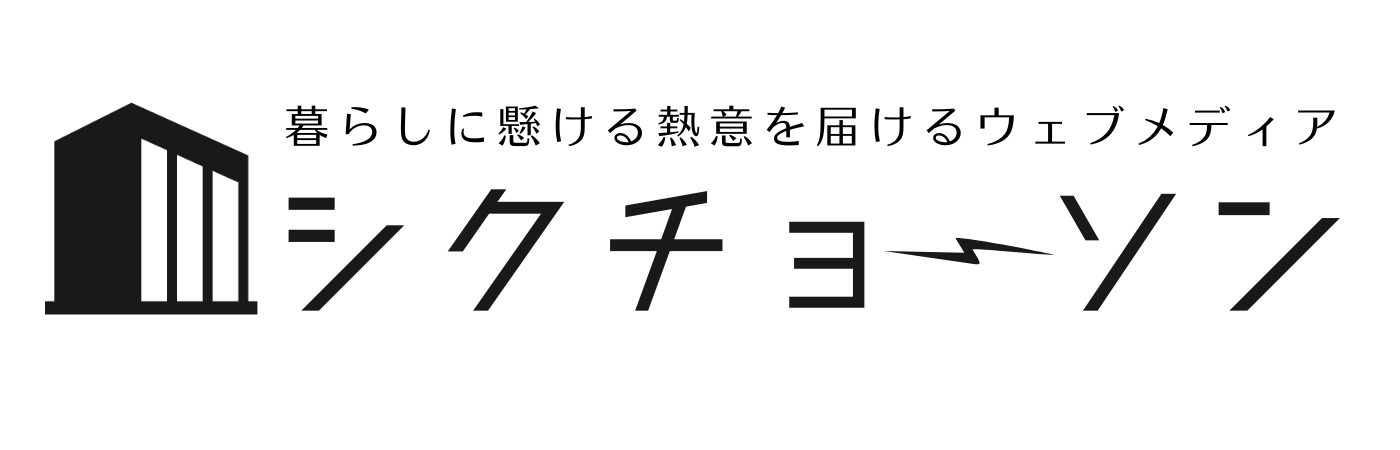防災DXとは、デジタル技術を活用し、災害対応の迅速化・精度向上を目指す取り組みです。
デジタル庁の方針では、自治体・企業・住民がリアルタイムで情報を共有し、最適な防災・減災対応を行うことを目指しています。単なるデジタル化ではなく、AI・IoT・ビッグデータを活用し、防災対策を根本から変革する取り組みが進んでいます。
自然災害の多い日本においては、このDXの概念を防災に取り入れた「防災DX」という言葉が生まれています。この記事では防災DXについて紹介します。
防災DXとは
デジタル庁による防災DXについての資料によれば、以下の3つがまず概要として掲げられています。
1.災害時に被害を迅速に把握し、的確に意思決定し、行動するためには「情報」が不可欠
2.国、地方公共団体、指定公共機関等がデジタル技術の活用によって災害情報を共有し、全体最適な災害対応を実行していくことが重要
3.また、住民等が平時から災害への備えを徹底し、災害時に命を守る行動を取れるよう、個人の状況に応じたきめ細かな支援が重要
そしてデジタル庁国民向けサービスグループは、関係省庁・地方自治体・民間企業等との連携を図りつつ、住民支援のための防災アプリ開発・利活用の促進等と、これを支えるデータ連携基盤の構築等の取り組みをはじめている、と述べています。
つまり、現在日本では災害対策、さらなる防災の一環として「防災DX」という取り組みが始まっている、というわけです。

防災分野における「データ連携基盤」とは
デジタル庁の防災DXの取り組みのうち、キモになっているのは「データ連携基盤」の構築です。
データ連携基盤とは、国・自治体・企業が保有する防災情報を統合し、災害時にリアルタイムで活用できる仕組みです。
たとえば、以下のような情報が一元管理され、迅速な対応が可能になります:
- 避難所の開設情報や混雑状況
- ライフライン(電気・水道・ガス)の復旧状況
- 災害時の交通規制・緊急ルート
現在、デジタル庁では「防災情報共有システム(Lアラート)」や、マイナンバーカードを活用した個人情報管理の仕組みを開発中です。
災害時に考えられるアプリやサービス例
データ連携基盤のプロトタイプ実証イメージではマイナンバーカードやマイナポータルを活用し、「氏名」「住所」「性別」「生年月日」の基本4情報と、避難時、応急時などの各フェーズで発生する個人の属性に関する情報の入力と活用をワンスオンリーで実現する考えです。
◆災害時に役立つ最新の防災アプリ・サービス
- Lアラート(公共機関からの災害情報を配信)
- 防災アプリJ-anpi(安否確認・避難情報を提供)
- AI防災チャットボット(自治体の問い合わせ対応を自動化)
- 衛星通信対応アプリ(Starlinkとの連携による通信確保)
これらの技術を活用することで、自治体・住民双方の災害対応力が向上しています。
住民の基本情報とフェーズごとのアプリ活用の内容がデータ連携基盤に集約され、各省庁の対応やライフライン事業者、交通事業者などのインフラへも一挙に連携が取れる仕組みです。
連携の根幹にはマイナンバーが存在しており、2024年5月末に話題になった岸田総理大臣とApple社のCEO ティム・クック氏の会談で「マイナンバーカードの機能をiPhoneに搭載する」と話が挙がったのも、データ連携基盤や防災DXに向けた布石でした。
事実、デジタル庁の本件に関するページにも、マイナンバーカード機能がスマートフォンに搭載されるメリットとして「様々な行政手続や民間サービスのオンライン申込、健康保険証や図書館カードなどの利用のほか、災害時や救急時などの利用など、利用シーンの拡大が進められています」と記載されています。
今後は多くのスマートフォンにマイナンバーカードの機能が搭載される見込みです。
災害時の通信インフラ問題と最新の技術活用
防災DXの普及により、災害時の情報共有は大幅に向上しました。しかし、通信インフラの維持・確保は依然として重要な課題です。
大規模災害時には、電力供給の停止や通信基地局の損壊、ネットワークの輻輳(ふくそう)などにより、スマートフォンやインターネットが利用できなくなる可能性があります。
こうした課題を解決するため、自治体や企業は新たな通信技術の導入を進めています。
また、ネットワーク帯域が使える状況であったとしても、個々のスマートフォン端末の充電容量にも限りがあります。とくに災害時は“超緊急時”以外は電源を切る、省バッテリー運用をすることも多く、電気や電力の運用へ気を回す必要も出てくるのです。
ひとえに防災といっても、デジタル技術を活用するだけがすべてではないのも事実です。先端的な取り組みのうち、デジタル部分とアナログ部分の併用や切り分け、有事の際の緊急インフラの整備なども求められています。
最新の通信技術・対策
こうした通信や充電に関する課題に対して、自治体などでもすでに対策を打ち始めています。
✅ Starlink(スペースXの衛星通信)
- 災害時、地上の通信インフラが破損しても、衛星インターネットにより通信が確保可能
- 2024年から日本の自治体で導入が進んでおり、実際に試験運用を開始している地域も増加
✅ ローカル5Gの活用
- 地方自治体が独自に運用できる「ローカル5G」を活用し、災害時の通信インフラを確保
✅ ドローン通信リレーシステム
- 災害発生時にドローンが通信中継局として機能し、被災地のインターネット接続を確保
- すでに実証実験を開始
✅ EV(電気自動車)の非常用電源活用
- EV(電気自動車)を非常時の電源として活用する動きが全国で進行中
防災DXの普及により、災害時の情報共有は大幅に向上しました。しかし、通信インフラの維持・確保は依然として重要な課題です。
大規模災害時には、電力供給の停止や通信基地局の損壊、ネットワークの輻輳(ふくそう)などにより、スマートフォンやインターネットが利用できなくなる可能性があります。
こうした課題を解決するため、自治体や企業は新たな通信技術の導入を進めています。