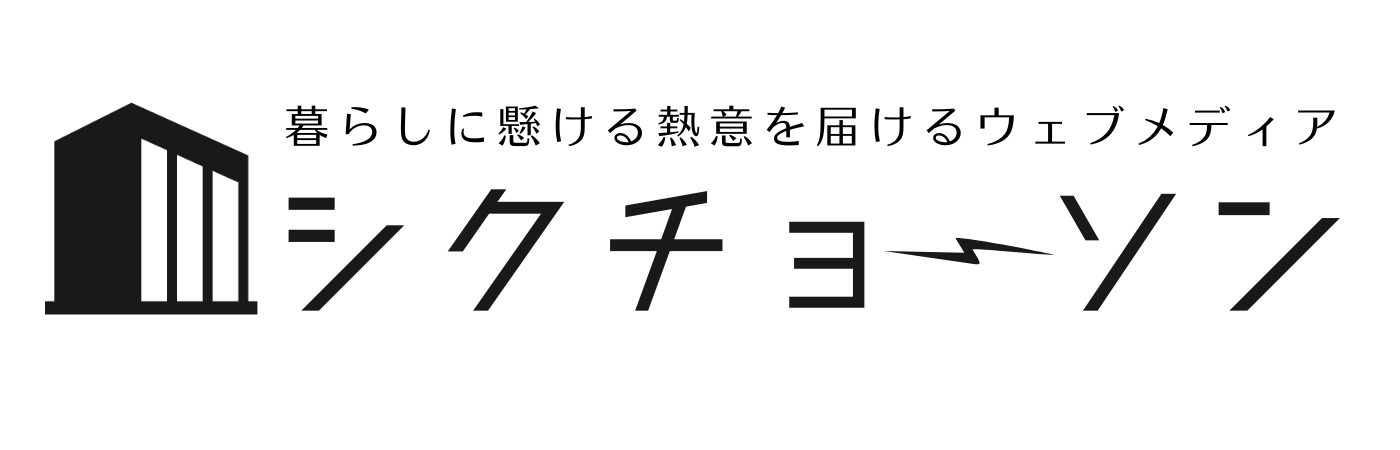目次
地域おこし協力隊の概要と役割
地域おこし協力隊とは、都市地域から過疎地域などの条件不利地域に移住し、地域振興活動を行いながら定住を目指す制度です。2009年に総務省が制度化し、令和5年度末時点で7,200人以上が活動しています。
主な活動内容は以下の通りです。
- 地域ブランドや特産品の開発・販売・PR
- 農林水産業への従事
- 観光促進や地域イベントの企画・運営
- コミュニティ活性化活動
- 環境保全、教育、医療などの地域課題解決
隊員は1~3年間の任期で活動し、自治体から報酬(概ね月額20万円程度)が支給されるほか、住居費や車両手配などの支援を受けられる場合もあります。
三重県地域おこし協力隊サポートデスクとは?
三重県では、地域おこし協力隊の円滑な受け入れと定着を支援するため、「三重県地域おこし協力隊サポートデスク」を設置しています。ここでは、
- 隊員の活動支援
- 相談窓口の提供
- 定着促進のためのネットワーク作り などが行われています。
サポートデスクを活用することで、自治体側は募集・受け入れの課題を相談でき、隊員側も活動中の悩みや定住に向けた課題を解決しやすくなります。
地域おこし協力隊の成功する自治体と「ひどい」自治体の違い
地域おこし協力隊は、自治体によって受け入れ体制やサポートの質に大きな差があります。成功している自治体と、そうでない自治体の違いを見ていきましょう。
成功する自治体の特徴
- 明確な目的とビジョンがある:隊員に求める役割が明確で、ミッションが共有されている。
- 受け入れ体制が整っている:隊員の相談窓口があり、地域住民との関係構築を積極的に支援。
- 定着・定住に向けた仕組みがある:任期後の就業・起業支援が充実。
「ひどい」自治体の特徴
- ミッションが曖昧:何をしてほしいのかが不明確で、隊員が手持ち無沙汰になりがち。
- 人材補填として利用:行政の雑務や単純労働を任せるだけで、隊員の強みを活かせない。
- サポート不足:受け入れた後のフォローがなく、隊員が孤立しやすい。
実際に、総務省のデータによると、2019年度に任期途中で退任した隊員のうち、17.5%が「自治体・住民とのミスマッチ」を理由としています。
地域おこし協力隊の離職・定着率と課題
地域おこし協力隊の制度設計上、任期終了後の定着率は重要な指標です。過去の統計では、
- 定住率:62.8%(うち50.8%が同一自治体、12.0%が近隣自治体)
- 他の地域へ転出:21.0%
定住に成功した隊員のうち、
- 43%が就業
- 36%が起業
- 13%が就農・就林 というデータがあります。
この数字からも分かるように、自治体が隊員の定住支援をしっかり行うことが、成功のカギを握っています。
まとめ:地域おこし協力隊を成功させるために
地域おこし協力隊を活用する自治体は、以下のポイントを押さえることが重要です。
- 目的と活動内容を明確にする
- 受け入れ体制を整え、定期的なサポートを行う
- 隊員のキャリアパスを考慮し、定着支援を充実させる
一方で、適切な受け入れができていない自治体では、ミスマッチが起こりやすく、「ひどい」という評判につながる可能性があります。成功事例を参考にしながら、自治体側の準備を万全にすることが求められます。