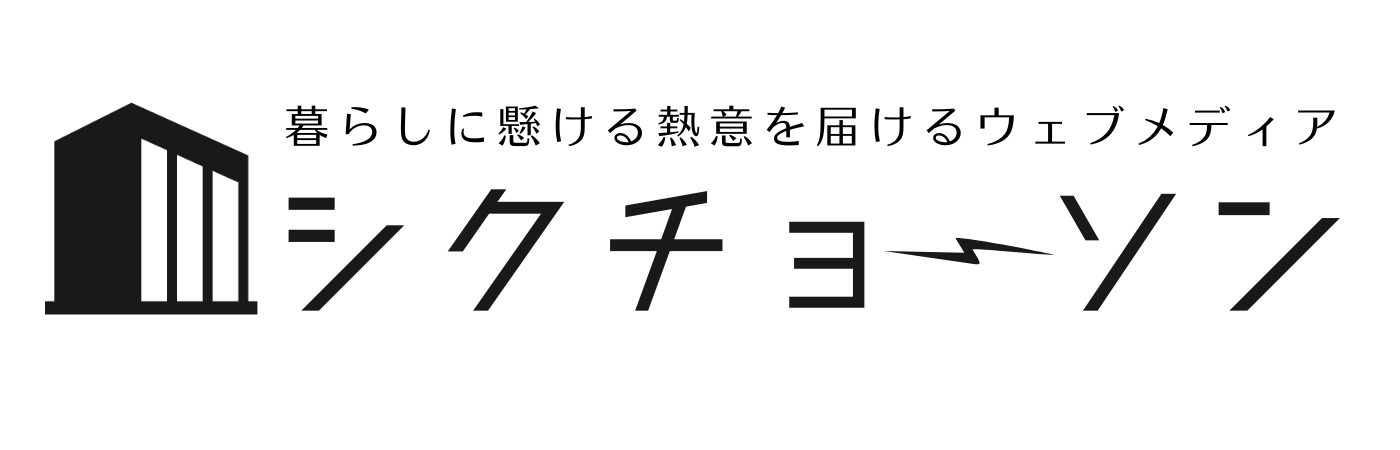フォースタートアップス株式会社は11月12日(火)から14日(木)の3日間、成長産業に特化した国内最大規模のカンファレンス「GRIC2024」を開催した。
14日(木)はオフラインDAYとして、渋谷ヒカリエにて展示やピッチイベント、セッションが実施された。本稿では実施されたセッションのなかから「日本食×○○ グローバル市場における日本食の新たな可能性」のレポートをお届けする。
登壇したのは、山田早輝子氏(株式会社FOOD LOSS BANK/代表取締役社長、Sports Doctors Network COO/アジア代表)と和田彩加氏(株式会社BETTEI CEO)。ファシリテーターは、梅澤高明氏(CIC Japan会長、A.T. カーニー 日本法人会長 / フォースタートアップス株式会社 社外取締役)が務めた。
ミシュランの星を獲得した店の8割に器を納品
まず、和田氏は「日本食×○○」の○○に入る言葉について、3つのコンテンツを挙げた。
ひとつ目は「日本の水」だ。和食、特に日本酒、だし、梅、豆腐、そばなどは、日本の水と組み合わされるとおいしさが増す。これは科学的にも証明されており、日本の軟水はグルタミン酸の抽出を促し、米の甘みを引き出す効果があるそうだ。日本食は世界的に広がりを見せているものの、食材としての「水」に着目した展開には、まだ多くの可能性が秘められている。良質な米や職人は海外に進出しているが、日本の良質な水と共に食材を提供することで、さらなる可能性が生まれると和田氏は考えている。
ふたつ目は「和食器」を挙げた。和食器は、食に付随する文化以上の存在であり、視覚的な楽しみを提供してくれる。歴史的価値を持つ器をアートとして楽しむことで、日本文化の継承にも繋がる。また、金継ぎなどのサスティナブルな取り組みは、日本人が長年培ってきた文化。魯山人の「器は料理の着物だ」という言葉にもあるように、食材、職人、技術が一体となることで、さらなる可能性が生まれるはずだという。
ちなみに和田氏はアメリカで毎年「器展」を開催しており、ミシュラン2つ星のレストランに自ら器を運び、3日間で約800万円の売り上げを達成した経験を話した。関心の薄い地域においても、器と料理の組み合わせによる付加価値向上を実感したと述べた。
3つ目に挙がったのは「OBANZAI(おばんざい)」だ。京都のおばんざい、韓国のパンチャン、台湾のマンガサなど、日常的に食べられる惣菜は、各国の食文化に根付いている。弁当やにぎり飯・おにぎりのように、OBANZAIという言葉を再定義し、新しい日本食のジャンルとして確立することで、新たな可能性が生まれると和田氏は考えている。
明治時代以前の日本には牛肉を食べる文化はなかったものの、米、大豆を使った豆腐や味噌などの家庭料理は、無駄なく食材を活用する知恵が詰まっている。海外ではヘルシー志向の高まりから、豆腐やお味噌汁への関心が高まっているが、提供できる店が少ないという現状がある。おばんざいをカテゴライズし、家庭的で健康的な和食として再構築することで、新たな可能性が広がると和田氏は提言した。
梅澤氏は、和田氏のアメリカでの器販売の成功事例を高く評価し、おばんざいと水に着目した今後の展開について質問した。和田氏は、「器販売の際に、『OBANZAI Night(おばんざいナイト)』をニューヨークで開催し、器の使い方を提案することで、販売促進に繋げた」と経験を述べた。この取り組みは、器とおばんざいをセットで提供することで、双方の価値を高める効果があったそうだ。また、器の販売会がおばんざいへの関心を高めるきっかけとなり、相乗効果が生まれたと説明した。
梅澤氏は、ニューヨークの和食レストラン約450店舗のうち、ミシュランの星を獲得した店の8割に和田氏が器を納品しているという事実に触れ、日本食レストランの世界的な広がりについて質問した。2019年の農水省の調査では、世界に15万軒の日本食レストランが存在し、現在では20万軒に達している可能性がある。ただし、その多くは「なんちゃって日本食」であり、本物の日本食文化を伝えるためには、ミシュランの星付きレストランのようなトップエンドの店から食器文化を取り入れていくことが重要ではないか、と梅澤氏は話す。これは、トップダウンで文化が浸透していくことで、ミドルクラスのレストランにも波及効果が期待できると考えたためだ。
この梅澤氏の考えに対し、和田氏は、和食器文化は日本人に深く根付いており、高価な骨董品だけでなく、昔ながらの食器や伝統技術を用いた器をカジュアルな店でも活用することで、日本食の魅力をより広く伝えられると考えていると返した。海外の「日本食風レストラン」にも、本物の和食器を取り入れることで、より洗練された日本食体験を提供できるという考えだ。
また、「水」について梅澤氏は、だしやゆずのように、日本の食材が世界的に認知されることで、西洋料理をよりおいしく、健康的にする可能性を秘めていると共感を述べる。軟水と硬水の違いに着目した展開は、ハードルが高いものの、大きな可能性を秘めていると語った。
山田氏は、「おばんざい」のポテンシャルについて、おいしい料理を提供するだけでなく、「体験」を提供することが重要ではないかと言う。器を鑑賞するだけでなく、おばんざいを通して日本の食文化を体験することで、コンテンツ以上の価値を提供できると考えているそうだ。
おにぎり(ONIGIRI)や寿司(SUSHI)、天ぷら(TEMPURA/TENPURA)のように、おばんざい(OBANZAI)も世界に広がる可能性を秘めたコンテンツであり、このような取り組みを通して、日本食固有の言葉がローマ字化され、世界標準で使われるようになることで、日本食の裾野がさらに広がると期待を寄せた。
和田氏は、おばんざいはビーガン、ベジタリアン、宗教上の理由で特定の食材が食べられない人々にも対応しやすい料理であり、ニューヨークで開催した「OBANZAI Night(おばんざいナイト)」では、ベジタリアンのお客様から好評を得たと話した。さまざまな食の志向に対応できる柔軟性がおばんざいの強みだ。
地域特性を生かした日本食×観光体験
梅澤氏は、食×観光というテーマで、自身が携わってきた事例を紹介した。
ひとつ目は、野沢温泉のオーガニックファームキャンプ。このキャンプでは、地元のオーガニックファームで収穫した野菜を使った料理を提供し、参加者は自然の中でゆったりとした時間を過ごしながら、人生について語り合う“時”を楽しめるそうだ。また、メディテーションやブナ林散策を通して、自然との一体感を感じられる体験を提供している。食だけでなく、水を中心としたローカルな食文化を体験できる点が特徴だ。
ふたつ目は、佐賀県嬉野市の「嬉野茶時(うれしのちゃとき)」。参加者は、お茶畑の上に設けられた特別な台の上で、農家さんが淹れた3種類のお茶を味わえる。梅澤氏らは、この体験に地元の日本酒や食材とのペアリングを取り入れ、付加価値を高めることに成功したようだ。
3つ目は、富士吉田市の食の街活性化プロジェクト。外国人観光客向けに、多言語メニューの作成、共通サイネージの設置、パンフレット作成、週末イベント開催などに取り組んだ。近隣にある富士急ハイランドのコンテンツを活用することで、街の活性化にも貢献したという。この取り組みはコロナの影響で一時中断したものの、現在は再開されたそうだ。
課題となる「発信力」は海外企業とのコラボで補う
山田氏は、日本食×○○のには「海外への発信」が入ると述べた。日本食は世界的に強いコンテンツだが、日本の発信力の弱さが課題であると最初に話した。
サスティナビリティに関しても、日本はSDGs以前から持続可能な取り組みを行ってきたにも関わらず、発信力不足から評価されていない現状がある。山田氏は、自身が経営するフードロスバンクでは、日本の素晴らしい食産物や食文化を海外に発信するため、ブルガリなどのグローバルブランドとコラボレーションし、サスティナビリティをテーマにしたチョコレートを開発。チョコレートにはフードロスになってしまう食材を使用し、パッケージには佐賀県の伝統工芸品である和紙を採用した。また、コロナの影響で困窮していた花屋から仕入れた押し花をチョコレートに添えるなど、社会貢献にも配慮した取り組みとなっている。これはすべて大手企業とのコラボレーションによって、課題である発信力を補った取り組みだ。そのほか、アルマーニやラルフローレンなどの海外ブランドとのコラボレーションを通じて、同氏らは日本の食文化とサスティナビリティへの取り組みを発信している。
また、山田氏は、国や業種を超えた取り組みとして、スポーツドクターズネットワークを立ち上げたことを紹介した。レアルマドリードのメディカルドクターをヘッドに、さまざまな国や業種の専門家が集結し、ハーバードメディカルスクールと共同で事業を展開しているそうだ。当初、ハーバードメディカルスクールのメニューには「食」の要素が欠けていたため、日本の長寿やスポーツ選手の食生活、ウェルビーイングといった日本の食文化の強みを伝えることで、日本の食がメニューに加わることになったという。
スポーツドクターズネットワークは、CEOはレアルマドリードのメディカルドクター、コンプライアンスオフィサーはノーベルファウンデーションの会長、そして山田氏はアジアでのビジネス展開をリードしている。また、PSG、マンチェスターユナイテッド、NFLなど、さまざまな分野、プロチームの専門家が参加しており、ハーバード大学医学部との共同研究や、イギリス議会でのプレゼンテーションなどにも取り組む。来年5月には、東京大学で食に焦点を当てたカンファレンスを開催する予定だそうだ。
「グローバル」と「ローカル」の区別はもはや古い概念
日本食はITや食医学など、さまざまな分野との掛け算で可能性を広げ、世界に発信していくことで、さらなる広がりを見せていくと山田氏は予測している。フードロスバンクは、日本の食文化を海外ブランドの力を通して世界に発信しており、グローバルブランドと協力することで、展開力を強化した。和田氏も、日本のサスティナビリティを海外に伝えるために、海外ブランドと連携し、食医学や栄養学に関する情報を発信しているそうだ。
和田氏は、フードロスバンクの活動に協力することで、日本人が古来から取り組んできたサスティナブルな活動を世界に発信できる意義を感じていると話した。また、おばんざいは健康や水の質への影響など、エビデンスに基づいた発信をすることで、さらなる可能性を秘めていると述べた。
参加者から、主要なマーケットについて聞かれた和田氏は、地方の食文化体験が、新たな「ごちそう」の概念になると考えていると話した。地方の食材や料理は、外国人観光客にとって魅力的なコンテンツであり、SNSでの情報発信を通じて、地方から世界への進出が成功する事例も増えているからだ。くわえて、「グローバル」と「ローカル」の区別はもはや古い概念であり、日本食はどちらにも当てはまる要素を持っているため、地方と首都圏の両方から発信していくことが重要だと述べた。知られていない地方の魅力を発掘し、海外の観光客と共有することで、日本食の可能性はさらに広がると期待を表明した。
山田氏は、グローバルな事業展開における最大の課題は、関係者それぞれの「わがまま」に対応することだと述べた。大手ブランドから農家名を伏せるよう要求された経験をふまえ、日本の食文化や食材に自信を持つことの重要性を強調した。また、慶應義塾大学大学院でクリエイティビティについて教えている経験から、スティーブ・ジョブズの「Creativity is connecting things.」という言葉を紹介し、広い経験を通して得た知識や経験を繋げることで、新たな発想が生まれると説明した。
最後に梅澤氏は、セッションを通してふたつのメッセージを提示した。ひとつ目は「掛け算の可能性」。さまざまな人や文化、食材、技術を組み合わせることで、新たな価値が生まれる可能性を強調した。ふたつ目は「世界との協働」。日本人だけで日本食を世界に広げるのではなく、世界で日本食を取り込み、新しいものを創造しようとしている人々と積極的に協力していくことの重要性を訴えた。