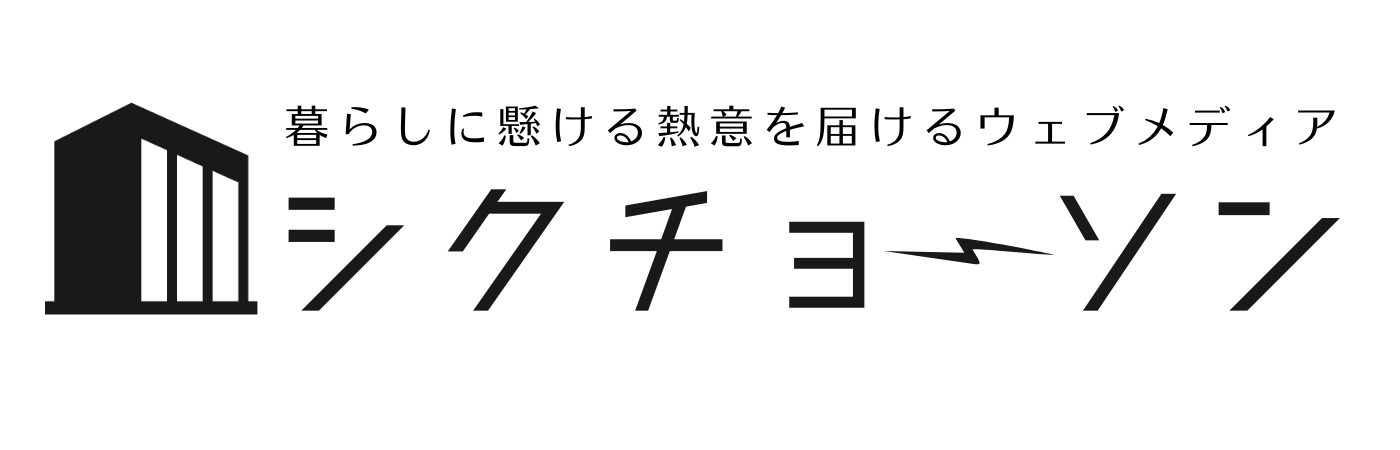自動運転大型トラックの開発に取り組むスタートアップ・株式会社ロボトラックが、東京大学協創プラットフォーム開発株式会社やPKSHAアルゴリズム2号ファンド、AIS CAPITAL株式会社などを引受先とする第三者割当増資により、シードラウンドで3億円の資金調達を実施した。
ロボトラックは、米国の自動運転企業Tusimple社で完全無人トラックの開発を成功させた共同創業者Nan Wu氏が、日本市場向けに設立した企業。世界最高レベルの自動運転技術とその実装経験を基盤に、日本が抱える「物流の2024年問題」への対応を進めている。
新東名での100km実証に成功 東京〜名古屋間の運行を目指す
ロボトラックは、経済産業省の支援事業にも採択されており、2025年2月には新東名高速道路・駿河湾沼津SA〜浜松SA間の100kmにわたり、レベル4相当の自動運転走行テストを実施し成功を収めた。
この成果を踏まえ、2025年11月には東京〜名古屋間(約300km)、さらに2026年中には東京〜大阪間(約600km)でのレベル4実証実験に着手予定。将来的には、東京〜名古屋間での完全無人トラック運行の実現を目指している。
また、効率化が求められる幹線物流のニーズに応えるため、トラクターヘッドへの対応拡大も視野に入れている。
産官学と連携し、インフラ構築と量産体制を加速
ロボトラックは、物流事業者やインフラ関連企業との連携も強化。実証実験を重ねながら、社会実装と量産体制の整備を進めていく方針だ。
代表のNan Wu氏は、「Tusimple時代に築いた技術と実績を活かし、物流現場の声に応える形で開発を進める。東京〜名古屋、そして東京〜大阪への完全無人走行の実現を通じて、日本の物流課題に革新をもたらす」と語っている。
地方と幹線物流に新たな可能性を
今後、地方の物流拠点や中継基地と都市間輸送のハブをつなぐ形で、ロボトラックの技術が実装されれば、ドライバー不足や過重労働といった構造的課題の緩和に貢献することが期待される。
自動運転トラックという次世代モビリティの社会実装は、単なる技術革新にとどまらず、地域経済やインフラ再構築と深く結びつく。ロボトラックの挑戦は、物流を基盤から変える「地方創生×技術革新」の象徴といえるだろう。