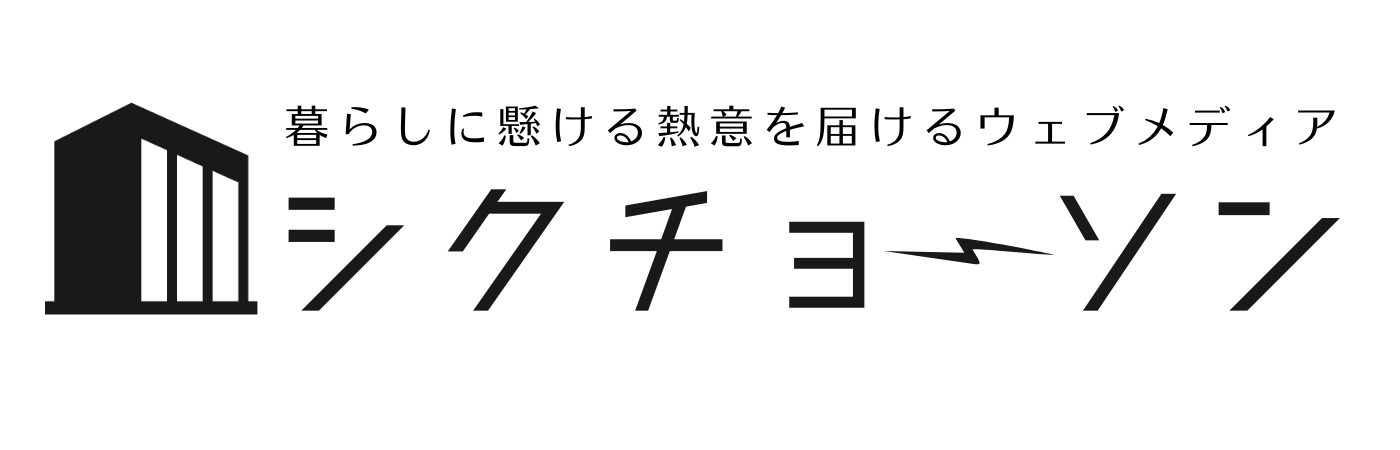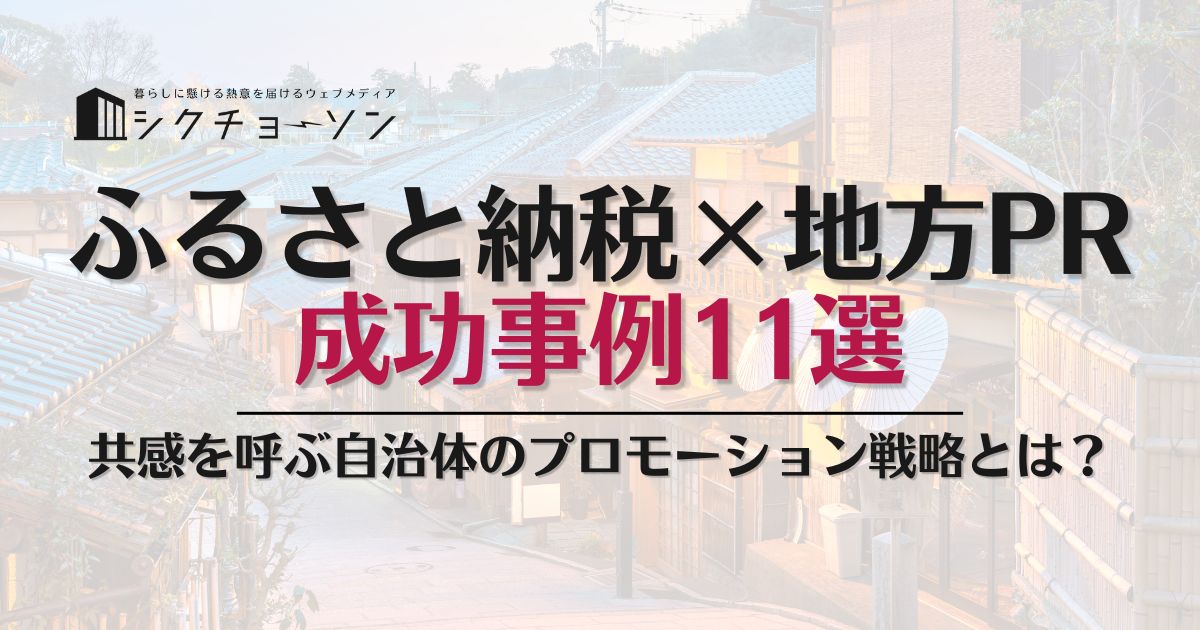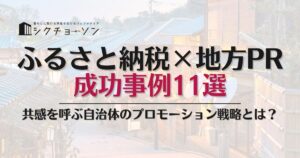ふるさと納税制度は、寄附を通じて地域を応援できる仕組みとして広く定着しましたが、自治体間の競争が激化する中で、単なる「お得感」だけでは寄附を集めるのが難しくなってきています。
そこで注目されているのが「地方PR」という視点です。ただ商品を紹介するのではなく、その背景にある人や文化、課題への取り組みを伝えることで、寄附者に共感や納得感を持ってもらえるようになるのです。
たとえば、地域の若者と一緒に開発した返礼品、災害復興支援につながるプロジェクト型の寄附、地元企業と連携したブランディング施策など、地域のストーリーを丁寧に伝えることが大きな反響を呼んでいます。
こうしたPRは、一時的な寄附額の増加にとどまらず、地域への関心や関係人口の拡大、さらには観光や移住の促進などにも波及する可能性を秘めています。
ふるさと納税は「物を売る」のではなく、「地域とつながるきっかけをつくる」ものへ。これからのふるさと納税には、自治体の“伝える力”がますます問われる時代になっています。
【本記事でわかること】
✅ 共感を呼ぶストーリー設計・地域ブランディングの要点
✅ ふるさと納税を活用した地方PRの成功事例(11選)
✅ 寄附が集まる自治体が実践するプロモーション戦略
ふるさと納税×地方PRの成功事例11選|地域の魅力を伝える自治体の工夫とは
ふるさと納税の寄附額を伸ばすためには、「地域の魅力」をいかに伝えるかがカギになります。ただ返礼品を用意するだけではなく、その背景にある物語や取り組みを発信することで、寄附者の共感を呼び、地域との関係性を深めることができます。
ここでは、ふるさと納税を通じて地方PRに成功した事例を、テーマ別に紹介します。
社会課題と結びつけた共感型プロジェクト
北海道旭川市 × ネッスー株式会社|フードバンク支援で2000万円を集めた共創型ふるさと納税
ひとり親家庭などへの食支援を目的に、フードバンクと連携した寄附プロジェクトを展開。2000万円以上の寄附を集め、社会的意義と地域貢献が評価された事例です。
✅ この事例のポイント:社会課題(食支援)と返礼品を結びつけ、共感を得た寄附促進モデル

鹿児島県阿久根市|人口減少に立ち向かう「若者応援プロジェクト」
地域に残る若者を応援するふるさと納税プロジェクトを立ち上げ。「地域の未来を寄附で支える」という強いメッセージ性が、幅広い世代からの共感を呼びました。
✅ この事例のポイント:若者支援という明確なメッセージが、応援したい気持ちを引き出した好例

地域資源を活かした体験型の返礼品
横浜市|電車運転体験会という“リアル”な返礼品で話題に
市内を走るシーサイドラインの運転体験ができるという、他自治体にないユニークな返礼品を展開。メディアでも取り上げられ、都市部ならではの体験型プロモーションとして注目を集めました。
✅ この事例のポイント:都市型の地域資源を活かし、話題性と体験価値を兼ね備えた返礼品設計

高知県四万十町|カヌー体験や地元ガイド付きツアーを返礼品に(参考事例)
自然を活かした地域ならではの体験を返礼品に組み込むことで、観光との相乗効果も生まれています。体験を通じて関係人口化を狙う取り組みの一例です。
(外部事例)
✅ この事例のポイント:自然体験を通じた関係人口創出につなげるプロモーション施策
民間人材・地域プレイヤーと連携した広報戦略
千葉県館山市|起業人との協働で返礼品と広報を刷新、寄附額6億円超に
地域活性化起業人の知見を活かし、魅力的な返礼品の開発やSNS・PRの強化を実施。前年比162.3%の寄附増を達成するなど、外部人材活用の好例です。
✅ この事例のポイント:外部人材の力で返礼品・広報を刷新し、寄附額6億円超の成果を実現

宮崎県日南市|地域おこし協力隊とともにPR戦略を設計(参考事例)
地域の“担い手”と連携してブランディングを進めることで、地域内外の理解と共感を深めています。
(外部事例)
✅ この事例のポイント:地域おこし協力隊を巻き込んだ情報発信で、地域のストーリーを丁寧に発信
教育や人材育成と結びつけた寄附設計
山梨県立笛吹高校 × ふるなび|農業クラウドファンディング型ふるさと納税
将来の農業担い手育成を目的に、高校生と連携したふるさと納税型クラファンを実施。教育×地域課題×寄附という三位一体のPRが評価されました。
✅ この事例のポイント:高校生との協働による寄附設計で、教育・担い手育成の視点を融合

大分県豊後大野市|地元高校生とコラボした特産品開発(参考事例)
若者参画型の返礼品開発により、地域内での誇り形成と寄附者への新しい価値提案を両立させています。
(外部事例)
✅ この事例のポイント:若者参画型の返礼品開発で、地域内の誇りと外部評価を同時に高めた事例
データ活用や広告戦略を軸にした施策
長崎県波佐見町|ターゲット別広告運用で全国から寄附を獲得(参考事例)
SNS広告やリスティング広告を活用し、若年層にもアプローチ。ターゲット分析を元にした戦略的PRが功を奏しました。
(外部事例)
✅ この事例のポイント:SNS広告によるターゲット戦略で、寄附獲得の効率を最大化
佐賀県唐津市|LINE公式アカウントで寄附のリピーター獲得(参考事例)
寄附者との継続的な接点づくりにも注力。SNSやメルマガのような継続型メディアを活用することで、関係性構築にも成功しています。
(外部事例)
✅ この事例のポイント:LINEなど継続接点の活用により、リピーター寄附の仕組み化を実現
寄附を集める自治体に共通する「地域ブランディング」の考え方
ふるさと納税の寄附額を大きく伸ばしている自治体の多くに共通しているのが、「地域ブランディング」への意識の高さです。単に返礼品をPRするのではなく、その背後にある地域の価値やストーリーを伝えることで、寄附者の“心を動かす”アプローチを実現しています。
地域ブランディングとは、地域の強みや魅力を整理し、それを一貫したメッセージとして発信すること。ふるさと納税においては、以下のような視点がポイントになります。
- 「誰に届けたいか」を明確にするターゲット設定
例:若年層の家族向け、首都圏在住のシニア層など - 地域ならではの価値や背景を丁寧に伝える
例:地元企業のこだわり、伝統産業の継承、課題解決に挑む若者たちの姿など - 返礼品にストーリー性を持たせる
例:震災から復興した工房の商品、地元高校生が開発した新商品 など
特に共感を生みやすいのは、「地域に住む人々の想い」が伝わってくるようなプロモーションです。一方的な商品紹介ではなく、地域との“関係性づくり”を意識した発信こそが、継続的な寄附や関係人口の創出につながります。
地域ブランディングは時間のかかる取り組みですが、ふるさと納税のPRをその第一歩と位置づけ、寄附者との接点を戦略的に育てていくことが、これからの自治体に求められています。
ふるさと納税のプロモーション戦略|成功事例に学ぶ3つの設計ポイント
ふるさと納税で寄附額を伸ばすには、「何を届けるか」だけでなく、「どう届けるか」の設計が重要です。前章で紹介した成功事例からは、単に魅力的な返礼品を用意するだけでなく、プロモーションの設計段階から戦略的に動いていたことが共通点として見えてきます。
ここでは、事例から見えてきたプロモーション設計の3つの視点を整理します。
1. ターゲットを明確に設定する
成功事例の多くは、寄附者像を明確に定めています。たとえば:
- 地元出身のUターン希望者(関係人口候補)
- 食品にこだわりを持つ子育て世代
- 社会貢献意識の高い寄附者層(社会課題と共感)
ターゲットが明確であれば、どんな表現で訴求すべきか、どのチャネルを使うべきかも自然と定まります。
2. メッセージとストーリーを磨く
成功事例では、「単なるモノの紹介」にとどまらず、“なぜその返礼品なのか”“地域が抱える背景課題”まで含めたストーリー設計がされています。
- フードバンク支援、担い手育成、復興支援など、共感を呼ぶストーリー性
- 起業人や高校生などの“人”を主役にしたプロモーション
こうした背景をしっかり伝えることで、寄附者との心理的距離を縮めることができます。
3. 媒体ごとの活用戦略を設ける
媒体ごとに適したコンテンツの出し分けも重要です。
| メディア | 活用方法 |
|---|---|
| Web広告 | ターゲティング精度を活かした寄附促進 |
| PR動画 | 雰囲気や空気感を“体感”してもらう |
| SNS | 情報の即時拡散、共感コメントによる二次波及 |
| 自治体公式サイト | 信頼感と網羅的な情報提供の場として設計 |
特に近年は、SNSを使った動画・画像プロモーションが強い力を持つようになっており、視覚的な情報による“共感”と“拡散”が鍵になります。
ふるさと納税のプロモーションは、「感情に訴えるブランディング」と「論理的な訴求設計」の両輪で進めることが成功のポイントです。
ふるさと納税をきっかけに広がる地方創生の好循環とは?
ふるさと納税は、寄附金による財源確保だけでなく、うまく設計すれば自治体の未来につながる“関係づくりの起点”になります。特に近年は、ふるさと納税を地域PRやブランディングの文脈で活用する動きが広がっており、さまざまな波及効果が生まれています。
関係人口の創出につながる
体験型の返礼品や地域プレイヤーとの共創プロジェクトは、単なる一度きりの寄附で終わらず、地域への関心を持続させるきっかけになります。
「また来年も寄附したい」「現地に行ってみたい」という心理的なつながりは、関係人口の創出や将来的な移住・交流人口の増加にもつながります。
地域課題への共感と支援の呼び水に
社会課題に向き合う姿勢を打ち出すことで、「応援したくなる自治体」になることも大きな効果の一つです。
たとえば、ネッスー株式会社と旭川市のフードバンク支援のように、地域と民間が連携し、課題解決型のプロジェクトとして寄附を呼びかけることで、寄附者に“使い道の納得感”を与えることができます。
地域プレイヤーとの連携が進む
ふるさと納税の取り組みがきっかけとなり、地元事業者や教育機関との連携が生まれたり、民間の人材が広報や商品開発に関わることで、地域内のプレイヤー同士のつながりも活性化します。
結果として、地域の中で新たな価値創造や協働の動きが生まれやすくなります。
このように、ふるさと納税は「財源」ではなく、「人と地域をつなぐ仕組み」として設計することで、地方創生全体にポジティブな波を起こすことができるのです。
ふるさと納税は「関係づくり」の起点に|PRの視点を持つ自治体が選ばれる理由
ふるさと納税は、寄附額の多寡だけで語る時代から、「どれだけ地域の価値を伝え、つながりを生み出せるか」が問われる時代へと変化しています。
本記事では、地方PRとしてふるさと納税を活用した11の成功事例を紹介してきました。それらに共通するのは、単なる返礼品の魅力にとどまらず、「誰に」「どんな地域の姿を」「どう伝えるか」を丁寧に設計している点です。
社会課題と向き合う姿勢や、地域の人々の想いを伝えるストーリーは、寄附者の共感を呼び、関係人口の創出や持続的な支援にもつながります。
また、地域内外のプレイヤーがふるさと納税をきっかけに連携することで、自治体のブランド力そのものも高まっていくでしょう。
今後、ふるさと納税を活用した地方創生の取り組みはますます多様化していきます。だからこそ、制度を“財源確保”の手段として終わらせず、「地域と人をつなぐプロモーションの入り口」として捉える視点が求められます。
シクチョーソンでは今後も、ふるさと納税を通じた地域PRや共感型プロジェクトの事例を発信していきます。ぜひ他の記事も参考にしながら、地域の魅力を伝えるヒントとしてご活用ください。