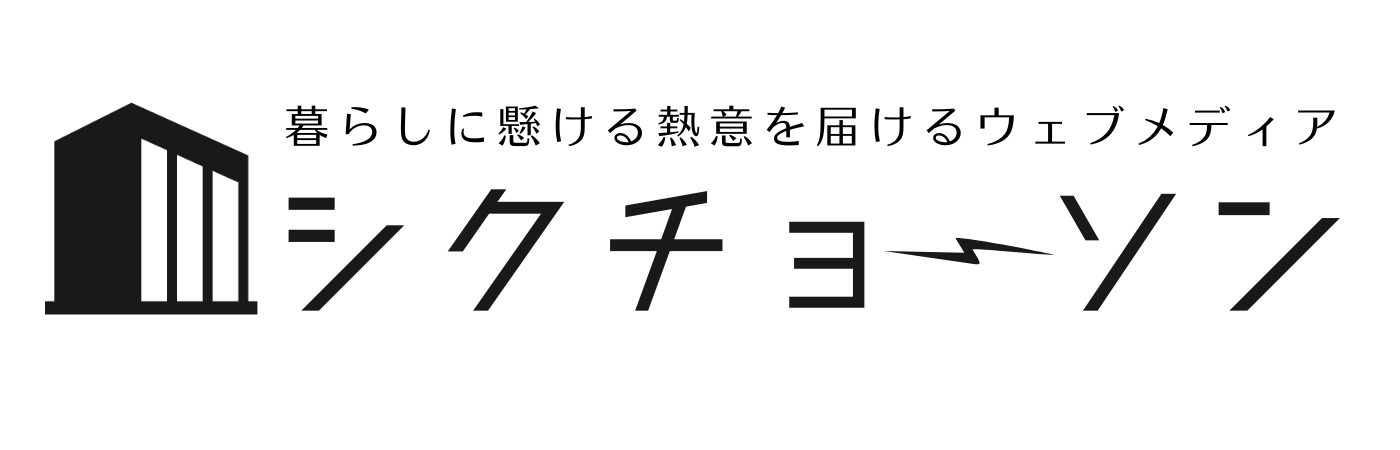スポーツは、地方創生の文脈でしばしば語られる。地域に根ざしたプロスポーツクラブが誕生し、地域の誇りとなる。試合が開催されることで観光客が増え、経済が活性化し、地域住民の結びつきが強くなる——。これは「スポーツによる地方創生」の一般的なイメージだ。
しかし、実際にスポーツクラブの運営を現実的に考えたとき、いくつもの課題が浮かび上がる。プロスポーツクラブは慈善事業ではなく、持続可能な経営を求められる。特に、フットサルのようにサッカーの縮小版として見られがちなスポーツでは、スポンサー収益や観客動員を確保することは簡単ではない。
それでも、この課題を克服することで、スポーツは地方創生の強力な推進力となる。湘南ベルマーレフットサルクラブは、その可能性を最大限に引き出すことに挑戦し続けている。株式会社湘南ベルマーレフットサルクラブ 代表取締役社長 佐藤 伸也氏に話を聞いた。
プロスポーツチームの枠を超える活動
湘南ベルマーレフットサルクラブは、Fリーグに所属するプロフットサルクラブだ。しかし、彼らの活動は単なる競技にとどまらない。社会貢献活動にも積極的に取り組み、地域に深く根を下ろした経営を続けている。
クラブの活動は多岐にわたる。地元企業との協力、自治体との包括連携協定、小児がん啓発活動など、さまざまな分野で存在感を発揮している。また、パソナJOB HUBと連携し、リモートワークの推進をはじめとする地域雇用創出等にも取り組んでいる。こうした活動がフットサルという枠を超えた社会的な価値を生み出している。
佐藤氏は2024年12月に実施したパソナJOB HUBとの連携協定に関する記者会見で、湘南ベルマーレフットサルクラブは社会課題を解決するためのハブ役になると話していた。
「パソナJOB HUB様と湘南ベルマーレフットサルクラブが今回の包括連携協定で目指すのは、この小田原市をはじめとする県西地域における“ハブ”になることです。地域内で何か課題に直面したとき、パソナJOB HUBと湘南ベルマーレフットサルクラブにその課題を投げ込んでいただければ、その都度必要な人材や企業、ステークホルダーを集結させて、その解決プロジェクトの旗揚げ役になることを目標にしています」
関連記事:
湘南ベルマーレフットサルクラブはなぜ「テレワーク講座」「起業家育成」に取り組むのか パソナJOB HUBと連携協定を締結した狙い
湘南ベルマーレフットサルクラブとパソナJOB HUBとの連携による施策第1弾として、2月6日にテレワーク人材育成講座を開催した。講師に株式会社aubeBiz 代表取締役 酒井晶子氏を招き、テレワークの基礎知識やテレワークの体験ワークを実施した。この取り組みの背景には、テレワーク実施企業は首都圏の一部企業に集中しており、地方圏ではテレワーク実施率が低い傾向がある。そのため、ホームタウンである西湘地域を中心に、新しい働き方の提案……つまりテレワークで働くことを目的として今回の講座が実施された。


クラブに所属する選手の地方創生・社会貢献
湘南ベルマーレフットサルクラブによるさまざまな社会貢献活動には、所属する選手が積極的に参加している点が非常に印象深い。今回、佐藤氏に取材したきっかけは、こうしたチーム単位・運営する企業単位の話だけでなく、選手による活動がとても活発だったからだ。
プロ・アマ問わず、スポーツチームによる地域貢献や地域振興などの取り組みは数多い。だが、湘南ベルマーレフットサルクラブに所属する選手は“自分事”として地域貢献活動に取り組む。
「うちのクラブの選手たちは、試合での活躍だけでなく、地域の一員として活動することを重視しています。契約時にはクラブのビジョンや地域との関わりをしっかり説明し、それに共感してもらえる選手だけが所属しています」と佐藤氏は語る。
2024年11月には、ひとり親家庭の方々を対象にした「スポーツ選手の夢キャリア教室」を実施した。このイベントのフットサル体験には湘南ベルマーレフットサルクラブ所属の牧野謙心選手が参加。牧野選手は、児童養護施設への訪問を積極的に行うなどまさにクラブの事業戦略である「競技生・事業性・社会性」を体現するプレーヤー。自身もひとり親家庭で育った経験を持つことから、この企画に賛同したという。

佐藤氏は「選手が地域活動に参加することで、地元の人々と直接触れ合い、その結果クラブのファンが増えていく。結果的に、スポンサーの増加や試合の観客動員にもつながります」とクラブの運営方針について説明する。
スポーツクラブと地域社会の関係は、単なる興行イベントにとどまらない。選手自身が地域と関わりながら、社会貢献活動を通じてクラブの価値を高めているのだ。そしてこのチームとして歩もうとする道のりを、選手一人ひとりにも浸透しているのが湘南ベルマーレフットサルクラブの最大の特徴である。
経済性×社会性×スポーツという高い壁への挑戦
スポーツクラブの運営は、経済的な視点と社会的な視点のバランスを取る必要がある。スポーツチームはしばしば「支援される側」として認識されることが多いが、湘南ベルマーレフットサルクラブはその概念を覆す。
実際、クラブの経営は地域企業や自治体とのパートナーシップによって成り立っている。選手たちは地域のイベントに積極的に関与し、その姿を見た企業が「共感」を持つことで、新たなスポンサーシップにつながる。そして、その資金がクラブの強化費に還元され、競技面でも好影響を及ぼす。単なる「社会貢献活動」ではなく、クラブ運営の一環として機能しているのだ。
一連の循環こそが湘南ベルマーレフットサルクラブが中小企業庁のローカル・ゼブラ企業推進事業に「ゼブラ企業」として採択された所以でもある。ゼブラ企業とは、経済成長と社会貢献の二面性を持って地域創生を推進する企業のこと。事業としてのフットサルと、選手も参加するさまざまな社会貢献活動によって、“今の時代に即した企業成長”を図っているのだ。
こうした湘南ベルマーレフットサルクラブによる取り組みは、スポーツチームを支援する企業に対する従来の「広告を出稿」だけではなく、社会貢献活動への“共創プロジェクト”でもある。つまりスポンサー広告だけで終わらせるのではなく、社会貢献活動にもつながる「ハブ」となるための明確な手段を確立しつつあるのが湘南ベルマーレフットサルクラブなのだ。

ファン・サポーターからの理解も
プロスポーツチームを成立させるには、運営する企業や団体、そしてそれを支援する企業等だけでなく、ファンやサポーターの存在も必要不可欠。
筆者にも強く応援しているプロスポーツチームがあるため、“ファン目線”で大変失礼ながらも佐藤氏に「ファンやサポーターから、“社会貢献活動”をやっている暇があるなら練習してほしい」といった意見は出てこないのか、と聞いた。すると意外な返答をもらった。
「当然、我々はプロスポーツチームである以上、常に勝利、優勝することだけを目指してシーズンを戦っています。
ただ、たびたび実施するファンの方に対するアンケートにおいて『ベルマーレフットサルクラブの社会貢献活動について知っているか』『社会貢献活動に取り組む湘南ベルマーレフットサルクラブを応援したいか』といった質問に対して、ほぼ100%の方がポジティブな回答をしてくれています。
もちろん短期的な『勝ち』だけを見据えるなら、ひたすらフットサルだけに取り組むほうがいいかもしれません。しかし、長期的に揺るがない『強さ』を求めるのであれば、多くのさまざまなファンに応援してもらえる、地域や社会に貢献できているチームを作っていくほか無いと思っています」
佐藤氏の返答からも、湘南ベルマーレフットサルクラブとして長く社会貢献活動に取り組んでいることや、選手が積極的にさまざまな活動に注力していることもあり、ファン・サポーターに「湘南ベルマーレフットサルクラブは社会貢献活動もしっかり取り組むクラブチームだ」という認識が浸透しているのがわかる。佐藤氏が話す、長期的な揺るがない強さのために、“今がある”ということもファンやサポーターには理解されているのだと感じる。
久光重貴という選手の存在
湘南ベルマーレフットサルクラブの社会貢献活動において、クラブ全体、そしてファンやサポーターにとって、久光重貴選手の存在が大きいことは言うまでもない。湘南ベルマーレフットサルクラブの社会貢献活動に関して決して外すことはできない話なので、ここで触れておきたい。
久光選手は2008シーズンに湘南に加入。2009年にはフットサル日本代表に選出される。チームのキャプテン就任などもあり、チームだけでなくフットサル界をけん引する存在だった。ところが、同年に骨髄炎を発症。歩行は困難と一時は診断された。それでも久光選手は競技復帰を実現した。
しかし、2013年、メディカルチェックで右上葉肺腺がんが発覚。根治は望めない状況だった。だが、久光選手は治療を継続しながら現役フットサル選手としてプレーすることを決意。ホーム最終戦にはピッチに復帰した。同時に、選手活動だけでなく、講演活動や命の授業などを通して、がんの啓発や自身の経験から得た想いを伝えてきた。
その後も闘病生活を続けながら現役のフットサル選手として活動を続ける。その姿は「ヒサと共に。」を合言葉に、フットサルだけでなく、Jリーグ湘南ベルマーレなど競技を越えた支援の輪が広がっていった。
2020年12月19日、惜しまれながらもこの世を去った。湘南ベルマーレフットサルクラブの特設ページには次のように記載がある。
最後まで現役選手としてプレーをし続け、地域の人々・企業と手を取り合い、小児がんに苦しむ子供と家族の日々生きるチカラを引き出していきました。 特に社会が抱えている課題に対し、地域の方々や企業と手を取り合い解決に向けて積極的に取り組んでおります。
これは小児がんの子供たちに希望の光を与え続けた久光重貴選手が見せてくれた姿勢そのものです。
私たちはこれを「久光モデル」と呼び、福祉、防災、教育などスポーツ領域を超えて、広く社会につながり、地域にとって必要だと言っていただけるクラブになります。
久光選手の精神は現在もクラブに受け継がれており、がん啓発活動だけでなく地域の支援活動の中心的な考え方として根付いている。
湘南ベルマーレフットサルクラブが示す「地方創生におけるスポーツの可能性」
湘南ベルマーレフットサルクラブは、単なるプロスポーツクラブではない。地域課題の解決に取り組み、「まちのチカラになれるクラブ」を目指している。
「スポーツクラブができることは、まだまだあるはずです。僕たちのような規模のクラブでも、工夫次第で地域に貢献できる。地方創生は、一部の大きなクラブや自治体だけのものではないんです」
湘南ベルマーレフットサルクラブの取り組みは、地方創生におけるスポーツの可能性を示している。競技としてのフットサルの枠を超え、地域社会にとっての価値を最大化する。その挑戦は、今後のスポーツクラブ経営のあり方を大きく変えていくだろう。
湘南ベルマーレフットサルクラブでは2026-2027シーズンまでに
- 競技性:アジアNo.1
- 事業性:神奈川No.1アリーナエンタメ
- 社会性:160の社会課題プロジェクトの実施
をそれぞれ達成することを目指している。
これからのスポーツクラブは、単なる「競技団体」ではなく、地域課題を解決するプラットフォームとしての役割を果たしていくべきだ。そのモデルケースとして、湘南ベルマーレフットサルクラブは、今後も新たな挑戦を続ける。

佐藤 伸也
株式会社湘南ベルマーレフットサルクラブ
代表取締役社長
神奈川県藤沢市出身。大学時代までサッカー部に所属しプロを目指すが、2000年総合建設業者へ入社し、医療コンサルタントに従事。2007年より株式会社ZUCC設立に伴い入社。フットサル施設運営・コンサルティングを務める。同時に、湘南ベルマーレフットサルクラブGMに就任し、Fリーグクラブの経営に携わる。2022年には同クラブ代表取締役社長へ就任。
X:@shinya_sato_vv