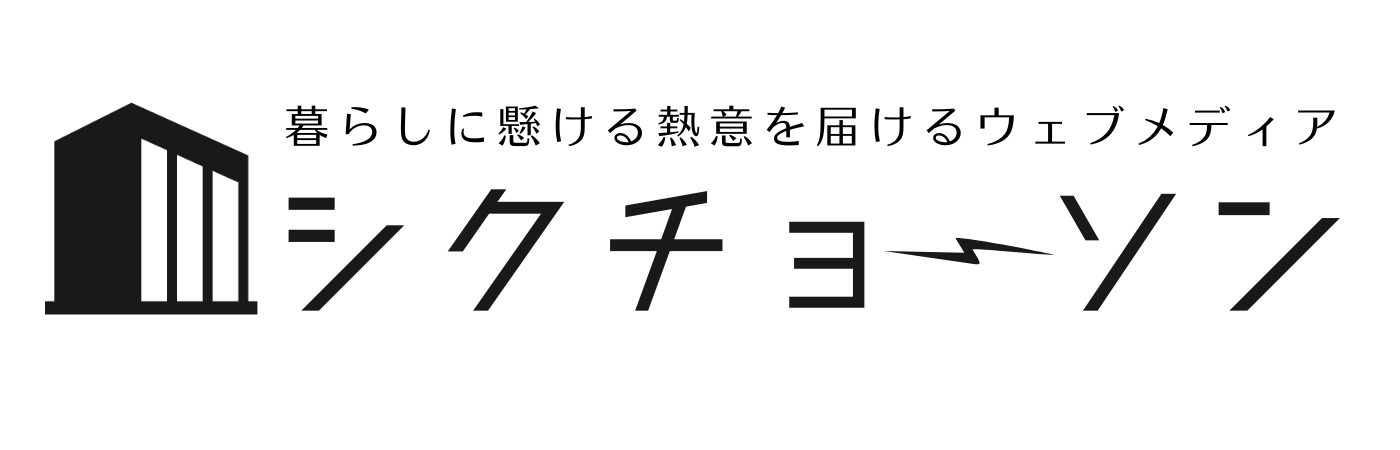都市部に本社を置くIT企業が、地方にニアショア拠点を構える動きが広がっている。人材確保や開発コストの最適化、リスク分散といった企業側の合理的な理由が多い一方で、その拠点が地域とどのような関係を築いているかについては、企業ごとに大きな差があるのが実情だ。
そうした中で、単なる「受託の場」を超えた“共創拠点”として注目を集めているのが、株式会社ニーズウェルによる長崎拠点での取り組みだ。
東京都に本社を構えるニーズウェルは、1986年創業の独立系システムインテグレーター(SIer)。金融・通信・医療・流通など、幅広い業界に対してシステム開発や業務改革支援を行い、クライアントのDX推進を支えてきた。同社は近年、ニアショア拠点として長崎県長崎市に開発センターを設置し、単なる開発拠点ではなく、地域との連携・人材育成・産学官連携など、多層的な関係性を築いている。
長崎県や自治体との関係性構築、地元大学との共同研究、スポーツ振興や女性活躍推進などの地域貢献。それらの取り組みは、業務効率の追求だけでなく、「地域とともに成長する企業」というビジョンのもとに動いている。
本記事では、ニーズウェルの長崎拠点を通じた“共創”の実践をひもときながら、IT企業が地域に根差すことの意味と、これからの地方拠点の可能性を探る。
なぜ今、長崎なのか──拠点立地とその戦略的意義
株式会社ニーズウェルが長崎拠点を開設したのは、2020年を予定していた計画を1年前倒しし、2019年に実現したものだ。拠点設立の背景には、業務効率化や人材確保といった経営戦略上の観点に加え、長崎という地域に対する企業としての親和性がある。
同社の代表取締役会長兼社長である船津浩三氏は、長崎県五島列島の出身。地元への思いも強く、「自分たちの事業が、ふるさとに何らかの形で貢献できるのではないか」という想いが拠点設立の原点にあったという。そうした背景に加え、長崎県・長崎市による企業誘致の施策が後押しとなった。補助金や採用面での支援制度が充実しており、地域としてもIT産業の誘致・定着に積極的だったことが、立地の決め手となった。
また、長崎大学、長崎県立大学、長崎総合科学大学など、地域内にIT人材の育成基盤となる高等教育機関が複数存在することも魅力のひとつだった。実際に、Uターン・Iターン希望者の採用にも手応えがあり、「地元で働きたい」と願う人材にとっての受け皿としても機能しつつある。
技術的な側面でも、通信インフラの高速化により、東京と遜色のない開発環境が構築可能となっており、物理的な距離が制約にならない時代の「持ち帰り型開発」の実現が可能となっている。かつては現場常駐が主流だった開発体制も、現在では案件単位での受託型へと移行が進んでおり、地方にいながら東京本社案件に参画できる仕組みが整っている。
ニーズウェルにとって長崎は、「地方の支社」ではなく、戦略的かつ地域密着型の拠点として、企業価値と地域価値の両立を目指す場所となっている。
東京と同じ品質で、地元に根ざす開発体制へ
ニーズウェルの長崎拠点が目指しているのは、単なる下請けやBPO業務の拠点ではない。本社と同水準の品質と育成体制を備えた“もう一つの開発中核”として、安定した長期開発体制を地域に根づかせる取り組みが進められている。
まず特徴的なのが、人材育成における教育体系の整備だ。長崎拠点では、東京本社と同等の教育プログラムを導入し、スキルレベルに関係なく段階的に成長できる仕組みを構築。IT未経験者や新卒人材も基礎から学び、確実に現場で活躍できるよう支援している。
また、開発体制についても、これまでの「常駐型」から“持ち帰り型”の請負開発へとシフトしている。これにより、社員は長崎に居住しながら、東京本社が受託する大規模プロジェクトに参加できる。地元にいながら高度な業務に関わることが可能となり、働きやすさと成長機会の両立が図られている。
さらに、長崎拠点では離職率の低さが大きな強みとして挙げられる。社員が地域に根ざして働くことで、職場への愛着や定着率が高まり、保守運用など長期にわたる案件を安定的に担当できる体制が築かれている。
こうした取り組みの背景には、「地方でも都市部と変わらない水準の仕事ができる」という確信と、「地域で働きたいという人の希望に応えたい」という企業の姿勢がある。
ニーズウェルは、拠点戦略においても“人に寄り添う”開発体制を実践している。
自治体や地域社会と築く、多面的な連携
ニーズウェルが長崎に拠点を構えて以降、地域との関係性は年々広がりと深まりを見せている。
同社は開設当初から、地元行政や地域社会との連携を“戦略的共創”の柱と位置づけており、事業の成長と地域課題の解決を両立する取り組みを継続的に実施してきた。
たとえば、長崎県・長崎市が実施する企業誘致制度や補助金制度の活用に加え、採用イベントやインターンシップの受け入れにも積極的に参加。県立大学や高校との連携も含め、地域内での雇用創出と人材育成の好循環を生み出している。
さらに、企業版ふるさと納税の活用や、Jリーグ・V・ファーレン長崎のスポンサー契約を通じて、地域への継続的な支援と貢献を行ってきた。特定の分野だけでなく、「地域全体の活性化」に向けた多面的な取り組みが特徴だ。
また、女性活躍の推進にも力を入れており、長崎県主催の「ながさき女性活躍推進会議」では自主宣言を実施。あわせて「長崎市男女イキイキ企業」としての認定も受けている。性別や年齢に関わらず働きやすい職場づくりを進めることも、地域社会との共生において欠かせない視点だと捉えている。
こうした取り組みは、単発的なCSR活動ではなく、長崎という地域に根差し、企業としての持続的な関係を築こうとする姿勢の表れである。
ニーズウェルは、行政・教育機関・スポーツ・雇用・福祉といった地域社会の多様な側面と接点を持ちながら、“IT企業としての在り方”そのものを地域とともに模索している。
大学との共創が拓く、産学連携の可能性
ニーズウェルが長崎での拠点運営を通じて力を入れているもう一つの軸が、大学との産学連携による共創の取り組みだ。
2024年には、長崎大学との共同研究により、生成AIを活用した2つのソリューションを開発。ひとつは決算書などの財務関連資料を自動作成する「FSGen(エフエスジェン)」、もうひとつは入札資格をAIで診断・判断する「QualiBot(クオリボット)」である。これらはすでに社内実務に導入されており、業務効率化や精度向上といった成果をもたらしている。
そして2025年以降、同社の産学連携はさらに医療分野へと広がっている。長崎大学病院の現場ニーズをもとに、医師のシフト編成を効率化するスケジューリングAIの開発を進めているほか、慢性疼痛治療に特化したAIソリューションの設計も始まっている。現場の課題と技術シーズを結びつけ、大学との連携の中で地域特有の社会課題に向き合う開発スタイルが実現しつつある。
また、同大学の情報データ科学部が実施する「実社会課題解決プロジェクト」にも参画。学生とともに課題を発見し、解決に取り組む実践的な学びの機会(PBL)を提供するなど、教育面でも深い関わりを持っている。
さらには、長崎県立大学との連携もあり、情報セキュリティ学科の学生を対象としたインターンシップの受け入れなども実施。地域の若手IT人材の育成と就業機会の創出にも貢献している。
このように、ニーズウェルの産学連携は、単なる研究開発の枠を超えて、人材育成・社会実装・地域課題解決の三位一体型モデルとして展開されている。拠点の立地を「地域課題に近い場所」と捉えるからこそ実現する、地方発・実装起点のテクノロジー共創が、今まさに進行中だ。
現場の声から生まれる、地域DXの芽
ニーズウェルが長崎で取り組んでいる産学連携や地域との共創は、単に外部との協力を進めるという話にとどまらない。むしろ、「現場にいるからこそ見える課題」に真摯に向き合い、それを起点とした技術開発やDX支援に取り組んでいる点に、同社の特長がある。
とりわけ医療分野においては、長崎大学病院との対話を通じて、現場から寄せられたニーズが新たなAIソリューションの発想につながっている。医師の勤務シフト編成を支援するスケジューリングAIや、慢性疼痛治療の臨床現場で役立つナレッジ支援AIなどは、いずれも病院の課題感と開発側の技術力が融合して生まれた取り組みだ。
こうした実践は、都市部に本社を持つIT企業だけでは見落としがちな「地域固有の課題に根差したDX」のモデルケースである。医療に限らず、高齢化や人口減少、地域交通、教育支援など、地方が抱える多くの社会課題は、現場に身を置くことでこそ真の輪郭が見えてくる。
ニーズウェルは、そうした課題に対して技術を“実装”するだけでなく、“共に発想する”姿勢を大切にしている。大学や行政と並走しながら、現場の声を起点としたテクノロジーの活用は、地方に根を張る開発拠点だからこそ可能な価値創造だ。
また今後は、医療分野だけでなく、地方中小企業のIT化や業務改善支援などへの展開も視野に入れており、地域経済の底上げにもつながるようなDX支援のかたちを模索している。
“地域の中でともに働き、課題を聞き、技術で応える”──その連続が、ニーズウェルの地域DXの本質である。
地域とともに成長する拠点を目指して
長崎拠点を「共創の場」と位置づけるニーズウェルの取り組みは、単発のプロジェクトではなく、中長期的な地域との関係構築を視野に入れたものだ。
今後、同社は拠点の体制強化にも注力していく方針で、早期に100名体制の実現を目指して採用活動を強化中である。
「地方に住みながら、都市部と同水準の仕事をしたい」という人材のニーズは年々高まっており、そうした人々にとってニーズウェルは、“地方でキャリアを築く”ための現実的な選択肢となりつつある。
さらに、長崎や九州エリアで注目が集まる半導体関連ビジネスへの貢献にも意欲を示しており、同地域における次世代産業の一翼を担う可能性もある。こうした産業的な広がりに加えて、今後も大学や行政との産学官連携によるソリューション開発を継続していく方針だ。
また、ニーズウェルが持つITソリューションの知見を活かし、地域の中小企業の業務効率化やIT化支援にも積極的に取り組んでいる。これは、地域全体の底上げを図るという点で、単なる自社拠点の強化にとどまらない意味を持つ。
ニーズウェルの長崎拠点が描いているのは、地方創生や地域産業振興に“共に働き、共に考え、共に成長する”企業拠点のあり方だ。それは受託業務の場でも、地域採用の手段でもなく、企業と地域がフラットに協働する“未来の拠点モデル”と言えるだろう。