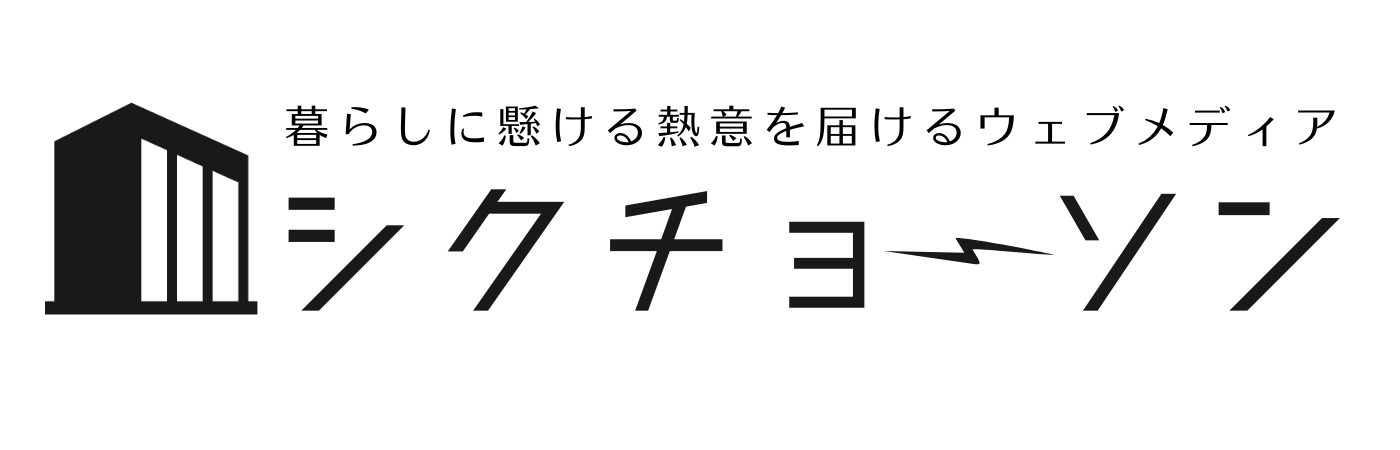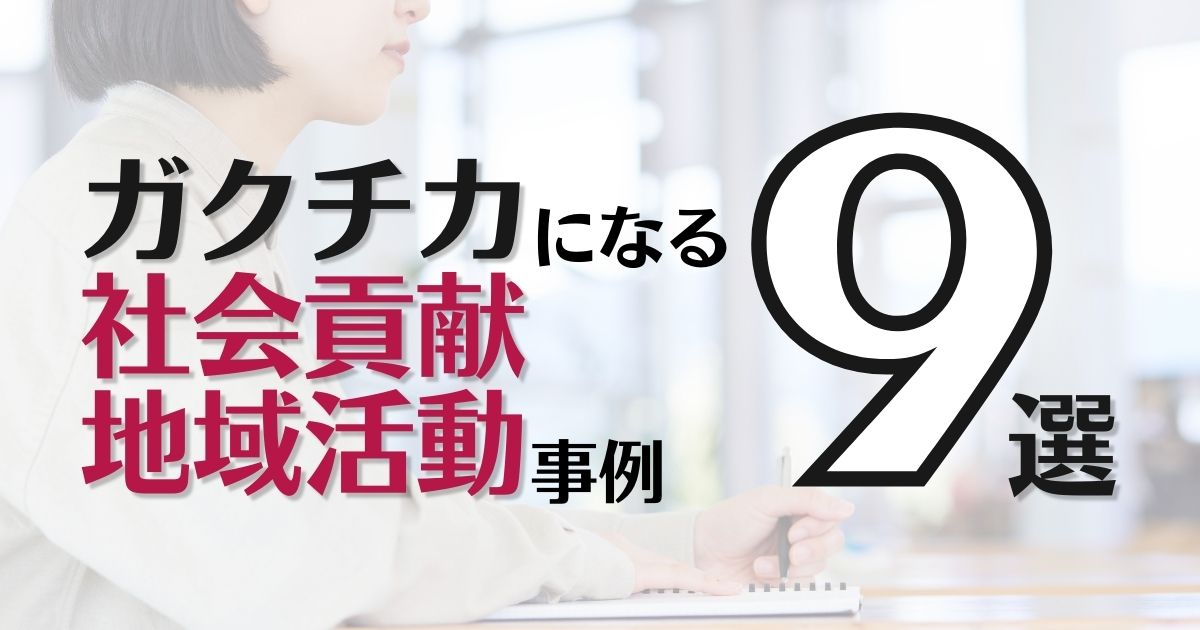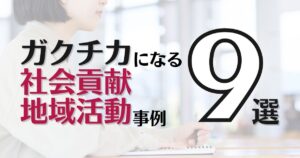就職活動において、面接官の印象に残る自己PRを作るためには「どんな経験を、どのように語るか」が重要になります。その中でも、近年注目されているのが「社会貢献」や「地域活動」といった実社会と接点を持った取り組みです。
特に地方創生や復興支援、防災、地域PRなどの活動は、単なるボランティアとは異なり、「課題に向き合う姿勢」や「人との協働」「自分なりの工夫や挑戦」が問われる場面も多く、面接官からの評価も高くなりやすい傾向にあります。
また、Z世代を中心に「社会的意義のある活動に取り組みたい」「地域と関わりながら成長したい」という価値観も広がっており、ガクチカに“地域での挑戦”を活かす学生が確実に増えています。
この記事では、実際に社会貢献や地域活動に挑んだ学生たちの事例を9件ピックアップし、その活動の中身や就活で活かすポイントまでを詳しく解説していきます。自分の経験をガクチカとしてどうアピールするか悩んでいる方に、少しでもヒントになれば幸いです。
ガクチカになる!社会貢献・地域活動の事例9選
近年では、地域課題の解決や防災、観光振興など、さまざまなフィールドで学生たちが主役となるプロジェクトが生まれています。ここでは、実際に大学生や高校生が主体的に関わった社会貢献・地域活動の事例を9件ご紹介します。
それぞれの活動が持つ社会的意義や就活でのアピールポイントもあわせて解説していますので、「自分ならどう語るか」を想像しながら参考にしてみてください。
防災・復興支援に挑んだ学生たち
「人の命を守る」「地域の未来をつなぐ」。そんな強い使命感を持ちながら、防災や復興支援の最前線で活動する学生たちがいます。これらの取り組みは、社会的意義が非常に高いだけでなく、チームでの協働や現場での臨機応変な対応など、就職活動における“ガクチカ”としても強く印象に残る経験になります。
ここでは、災害や防災をテーマに学生が主体となって動いた取り組みをご紹介します。
■ 高校生と作る「災害対応キッチンカー」プロジェクト(新田製パン)
兵庫県尼崎市の老舗パンメーカー・新田製パンは、防災をテーマにした日本最大級のキッチンカーを企画。このプロジェクトには地元高校生も参加し、災害時の炊き出し訓練や車両デザインのアイデア出しなどを担当しました。
高校生たちは防災意識を高めながら、実際に地域社会と連携し、課題解決に向けた“実践型の学び”を経験しています。
✅ この事例のポイント:防災×地域企業×高校生という三者連携で、社会課題を具体的に解決する力を体験

■ 「ゴミ拾いフェス」で全国の学生が防災・環境課題に挑む
鳥取県境港市で開催された「全日本学生選抜ゴミ拾いフェスティバル」には、全国から選抜された学生たちが集結。単なる清掃活動ではなく、防災教育や地域文化の発信もテーマに含まれており、イベントの企画・運営まで学生が主体となって行いました。
地域住民との交流や企業との連携を通じて、「まちを守る」ための多様なアプローチを体感した事例です。
✅ この事例のポイント:課題発見から実行まで、学生自らがプロジェクトを動かした総合力が光る

■ 復興の「今」を伝える番組を学生が制作(能登半島地震)
石川県の能登半島地震を受け、復興の現場に自ら足を運んだ学生たちが、被災地の現状や声を伝える番組を自主制作。報道・表現の力で支援の輪を広げようとする姿勢に、地域からも大きな反響がありました。
SNSや動画といった“Z世代らしいツール”を活かし、社会的メッセージを発信するスタイルが特徴です。
✅ この事例のポイント:「知ること」「伝えること」も立派な社会貢献。発信力を活かした地域支援の新しい形

■ 千葉県×学生による「防災×オープンデータ」アイデアソン
千葉県が主催する「アイデアソンコンテスト」では、防災や地域振興をテーマに、学生たちがオープンデータを活用した企画提案を行いました。地域の課題をデータで可視化し、実効性のあるアイデアとして形にする取り組みは、学生の柔軟な発想が光る好例です。
✅ この事例のポイント:データ分析・提案力・課題解決力を兼ね備えた“論理型ガクチカ”としても活用可能

観光・まちづくりに貢献した取り組み
地域の魅力を引き出す観光振興やまちづくりの分野でも、学生たちの活躍が目立っています。
若者ならではの視点や感性が、地域のPRやサービス改善、新たな価値の創出につながるケースは少なくありません。
ここでは、地域の魅力発信や課題解決に挑んだ学生の事例をご紹介します。
■ 郡山駅前に広がる復興アートとプロジェクションマッピング
福島県郡山市では、東日本大震災から14年を迎える節目として、学生たちがプロジェクトに参画。駅前に復興のメッセージを込めたアート展示やプロジェクションマッピングを企画し、地域住民とともに希望の光を発信しました。
震災を知らない世代が“今、自分にできること”を考え、表現した取り組みです。
✅ この事例のポイント:地域と「世代を超えてつながる」アートとまちづくりの実践例

■ 下関の観光を学生がデジタルでPR「デジコンしものせき」
山口県下関市では、観光振興の一環として学生主体の「デジタルコンテスト」を開催。高校生・大学生がチームで地域の観光資源を調査・分析し、PR動画やデジタルコンテンツを制作しました。
地域住民や行政とも連携しながら、若者の視点でまちの魅力を掘り起こす取り組みです。
✅ この事例のポイント:“観光×デジタル×若者”という、今の地域PRの理想形を体現

■ 学生が主導するEVカーシェアプロジェクト(共愛学園前橋大学)
群馬県前橋市では、大学生が地域のモビリティ課題を解決するべく、EVカーシェアの導入を企画・推進しています。交通課題×地域資源×若者の創意が融合したプロジェクトです。
✅ この事例のポイント:“サステナビリティ”という視点で語れる社会課題型ガクチカに最適

■ 「おてつたび」がZ世代の価値観を可視化|ニッチ観光への関心
「おてつたび」は、短期バイトと旅をかけ合わせたマッチングサービス。Z世代の学生を対象とした意識調査では、「有名観光地よりも、ニッチな魅力のある地域を訪れたい」と答えた人が93%にのぼりました。
学生の“旅の価値観”が地域の新しい観光資源のヒントにもなっています。
✅ この事例のポイント:「地域に貢献したい若者」の意識をデータで可視化した新しい形のガクチカ素材

学生団体・大学主体で進めるプロジェクト
地域や社会課題に挑む学生たちの中には、自ら団体を立ち上げたり、大学の授業・ゼミを通じて実践的なプロジェクトに取り組んでいるケースもあります。
こうした活動は「自ら考えて動く」姿勢が求められるため、就活においても「主体性」「課題解決力」「リーダーシップ」を伝える上で非常に有効なガクチカとなります。
■ 地方創生カレッジ「学生が主役の地方創生プロジェクト」
内閣府が推進する地方創生カレッジでは、大学の教員や学生が連携して、地方創生に関する映像コンテンツの制作を行っています。
その中でも「学生が主役の地方創生プロジェクト」というシリーズでは、実際に地域で活動する学生の視点から地方の魅力や課題が語られており、若者によるリアルな地域参画の姿が映し出されています。
✅ この事例のポイント:学生の目線で“地域を伝える力”を育む実践型コンテンツ制作

就活で活かすには?「伝え方」のポイント
せっかく社会貢献や地域活動に取り組んでも、それを就職活動でうまくアピールできなければ、ガクチカとしての効果は半減してしまいます。
面接官は「どんなことをしたか」だけでなく、「なぜその取り組みに挑んだのか」「どんな工夫をし、何を学んだのか」といったプロセスに注目しています。
以下に、社会貢献型ガクチカを活かすための伝え方のポイントと、参考となるミニ例文をあわせて紹介します。
「課題 → 行動 → 学び」の構造で伝える
ガクチカの基本は、「問題意識(課題)→ 自らの行動 → 結果・学び」というストーリー構造です。
地域活動は、社会的課題に直面しやすいため、この構造が自然と当てはまりやすいのが特徴です。
💬 ミニ例文:
「観光客が少ない地域に活気を取り戻したいと思い、大学の仲間と地元の魅力を伝える動画を制作しました。地域の方々との対話を重ねながら、情報発信の重要性と“伝え方”の工夫を学びました」
結果だけでなく「過程での工夫や苦労」も伝える
社会貢献や地域活動は、正解がない中で進めていくものが多いため、過程での判断や工夫が非常に重要になります。
💬 ミニ例文:
「ゴミ拾いイベントの運営に携わった際、住民の参加率が低いという課題がありました。どうすれば“自分ごと化”してもらえるかを考え、学生と地域の交流要素を加えることで、多くの方に参加いただけました」
業界ごとの“つながり”を意識して伝える
活動経験を話すだけでなく、「この経験が志望する業界でどう活きるか」までつなげると、より強い自己PRになります。
| 業界 | 活かし方の一例 |
|---|---|
| 観光・地域振興系 | 地域の魅力発信や観光資源の編集経験を活かせる |
| IT・デジタル | デジタルツールを活用した情報発信やDX文脈で語れる |
| 公共・行政 | 社会課題への向き合い方、関係人口創出の視点などが強みになる |
| 教育・人材系 | 若者の可能性を広げる活動から教育観を語ることができる |
💬 ミニ例文(行政志望):
「高校生と防災キッチンカーのプロジェクトに携わった経験から、行政と地域、民間が協力することで“住民に寄り添う支援”が生まれることを実感しました。この視点を活かして、地域住民の声を政策に反映できる行政職員を目指したいと考えています」
■ 4. 「自分がどう変化したか」を最後に添える
最終的には、「その経験を通じて、どんな価値観や強みを得たか」を言語化しましょう。
変化のストーリーがあると、面接官にとっても「人としての成長」が伝わりやすくなります。
💬 ミニ例文:
「活動を通じて、“行動することで地域は変わる”という実感を得ました。今後は社会の課題に対して、受け身ではなく、具体的な行動に移せる人でありたいと思っています」
“リアルな社会経験”が、就活における最大の武器になる
社会貢献や地域活動は、単なるボランティアや課外活動の枠を超えて、実社会との接点を持った“リアルな経験”です。
その中で感じた葛藤や工夫、チームでの挑戦、そして自分自身の変化は、就職活動において非常に説得力のある自己PR材料になります。
この記事で紹介した9の事例に共通するのは、「正解のない課題に向き合い、自ら動いた」という点です。
そして、そこには“社会のために行動する若者のリアル”がありました。
ガクチカとして語れることがない……と思っている人も、実は「ちょっと変わった地域での挑戦」や「仲間と一緒に作った企画」こそが、最大の武器になることがあります。
自分の経験を振り返る中で、今回の事例が少しでもヒントになれば幸いです。