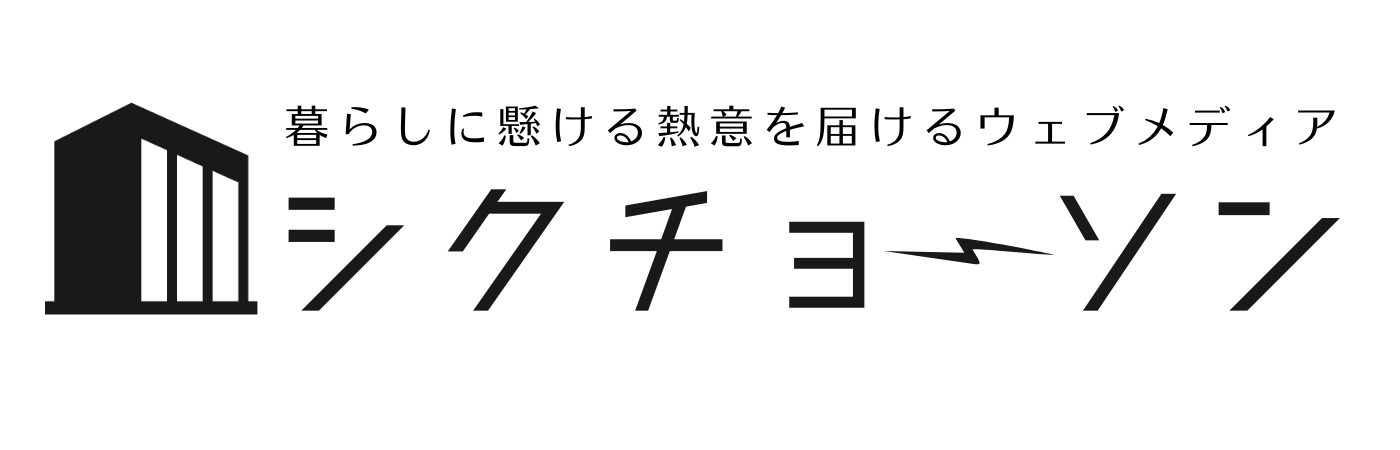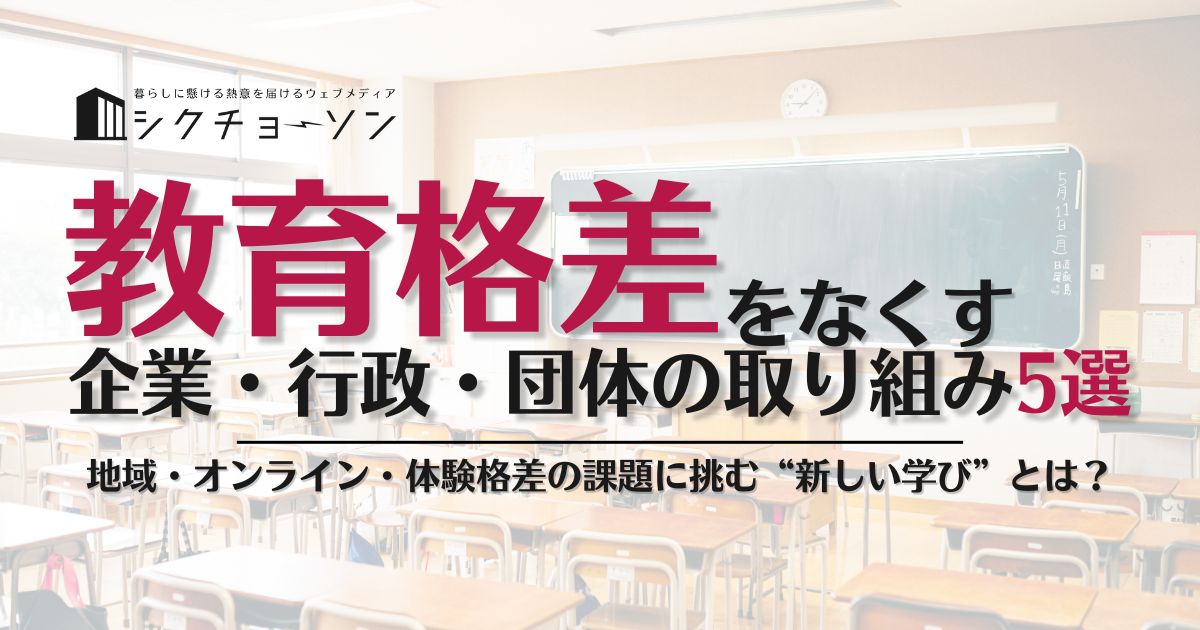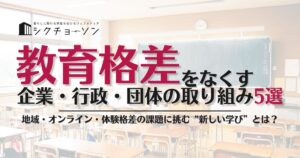「生まれ育った場所や家庭環境によって、受けられる教育の質が変わる」。そんな現実が、今の日本にも確かに存在しています。学力や進学実績といった数値に表れる格差だけでなく、ICT環境や体験機会、探究的な学びなど、見えづらい部分にも教育格差は広がっています。
このような課題は、もはや学校や教育行政だけで解決できるものではありません。現在では、企業やNPOなど多様なプレイヤーが「教育格差の解消」に向けた取り組みに乗り出し、地域社会と連携する動きが全国に広がりつつあります。
本記事では、教育格差という社会課題に真正面から向き合う企業の取り組みを紹介します。地方自治体との連携、クラウドファンディング、ICTの活用──それぞれの事例から、“新しい学びのかたち”を考えるヒントが見えてくるはずです。
教育格差とは?──地域・経済・体験…広がる学びの不平等
「教育格差」とは、子どもたちが生まれ育った環境によって、教育を受ける機会や質に差が生じることを指します。経済的な事情や地域ごとのインフラ差、さらには家庭の文化的背景など、さまざまな要因が複雑に絡み合いながら、子どもたちの将来に影響を及ぼしています。
一見すると見えづらいこの格差は、学力の差だけでなく、進学率や学習意欲、将来の職業選択にまで影響を与える重大な課題です。ここでは、代表的な3つの格差の現れ方を見ていきましょう。
家庭の経済状況による進学格差
家庭の収入によって、子どもが受けられる教育の選択肢は大きく変わってきます。学習塾や習い事、受験対策といった“追加的な教育投資”が難しい世帯では、学力の差が広がりやすく、進学先や将来の職業選択にも影響を及ぼします。
また、経済的理由から高校や大学への進学を断念せざるを得ないケースもあります。こうした経済的格差は、子ども本人の努力だけではどうにもならない構造的な問題となっています。
地方・都市部で異なる学習機会
地域によって、学習環境の充実度にも大きな差があります。都市部では進学塾や探究学習の機会が豊富である一方、地方ではアクセスできる教育資源が限られており、選択肢の幅が狭まってしまう傾向があります。
さらに、教員不足やICTインフラの整備状況など、学校そのものの支援体制にも地域格差が見られます。こうした“地域による学びの偏在”も、教育格差を生む要因のひとつです。
体験や探究学習の格差も深刻化
教育格差は、単に学力の差や進学率だけにとどまりません。近年注目されている「体験格差」や「探究学習の格差」も、子どもの成長に大きな影響を与えています。
例えば、博物館や美術館への訪問、スポーツや文化活動への参加、地域イベントへの関与など、日常の“学びの幅”そのものが、家庭環境や地域によって大きく異なります。こうした体験は学びへの好奇心や自己肯定感にもつながるため、見えにくいながらも深刻な課題といえるでしょう。
教育格差の解消に企業が取り組む理由とは
教育格差は、学校や教育行政だけでなく、社会全体で向き合うべき課題です。そうしたなかで、企業がこの問題に関わる動きが少しずつ広がっています。
理由のひとつは、企業にとって「教育」は決して無関係ではないということです。学びの機会を得られなかった子どもたちは、将来的に選択肢が限られ、社会とのつながりを持ちにくくなる可能性があります。それはやがて、労働力の減少や地域経済の縮小といった形で企業にも跳ね返ってくるかもしれません。
また、社会課題の解決に取り組む姿勢は、企業の信頼性や持続可能性を示す指標としても注目されています。SDGsやESGといったキーワードの広がりにより、「誰もが安心して学べる社会」を目指す活動が、企業価値の向上につながる時代になってきました。
さらに、教育支援に取り組むことで、地域との関係性が深まり、新たな人材との出会いや共創のきっかけになるという側面もあります。地域の未来を一緒につくるパートナーとして、企業が教育の現場に関わる意味は、これまで以上に大きくなっているのです。
教育格差の解消に取り組む企業事例
教育格差という複雑な課題に対して、全国ではすでに多くの企業や団体が具体的なアクションを起こしています。
ここでは、地域連携やテクノロジーの活用、体験機会の提供など、さまざまな切り口から教育の機会を広げようとする取り組みを5つ紹介します。
不登校の子どもたちに学びを|学費支援のクラウドファンディング
経済的な事情や学校環境に悩み、不登校になる子どもたちが増えています。中には、通信制高校などを検討しても学費の負担がネックとなり、進学をあきらめざるを得ない家庭も少なくありません。
そうした子どもたちに学びの選択肢を届けようと、NPO法人D.Liveと株式会社TMRがタッグを組み、「不登校の子どもたちの学費を支援する制度」設立に向けたクラウドファンディングを実施しました。
制度が整えば、民間からの寄付を原資として「本人・保護者・支援者」それぞれの目線で使いやすい学費支援が可能になります。
行政の制度では拾いきれない家庭に対して、民間主導で“もうひとつの進学の道”をつくる取り組みとして注目されています。

体験の格差を埋める|スポーツイベントによるひとり親支援
教育格差は、学力や進学率の違いだけではなく、「体験の格差」としてもあらわれます。旅行やレジャー、スポーツや文化活動といった日常的な体験は、学びの意欲や自己肯定感の土台になる大切な要素です。
こうした背景のもと、株式会社Casaと湘南ベルマーレフットサルクラブは、ひとり親家庭の子どもたちを対象にしたスポーツイベントを共同開催しました。参加したのは、神奈川県平塚市など県内各地の親子約40名。ベルマーレの選手たちとのミニゲームやキックターゲット体験を通じて、子どもたちは楽しいひとときを過ごしました。
この取り組みは、「体験する機会が少ない子どもたちに、思い出と学びの場を提供したい」という企業の思いから生まれたものです。学びの土台となる経験を地域ぐるみで届けることで、見えづらい格差に向き合う実践的なアプローチといえるでしょう。

地方にもオンライン学習の選択肢を|Schooと自治体の連携
都市部と地方での教育格差のひとつに、「学びの選択肢の偏在」があります。進学塾や探究学習、外部講師による特別授業など、都市部では当たり前に提供されている教育機会が、地方では十分に確保されていない現状があります。
この課題に対し、株式会社Schoo(スクー)は自治体と連携し、地方の学習機会を広げる取り組みを進めています。オンライン学習プラットフォームを活用することで、場所にとらわれず、全国どこからでも“質の高い学び”にアクセスできる環境を提供しています。
Schooはこれまでに、全国20以上の自治体と協定を締結し、地域の教育機関や学習支援団体と連携してきました。インターネット環境があれば、地方に住む子どもたちにも都市部と同じ学びを届けられる──。そんな未来の教育インフラとして、オンライン学習の可能性が広がっています。

不登校支援の“第2の教室”|品川区のオンライン授業施策
不登校の児童・生徒が増加する中で、「学校に行けない=学びが途切れてしまう」という状況をどう防ぐかは、教育格差の大きな論点のひとつです。
そこで、東京都品川区は、週20コマ・5教科のオンライン授業を不登校の子どもたちに向けて提供する取り組みを始めました。
授業はすべてZoomを活用し、区内の民間学習支援団体と連携して実施。自宅からでも授業を受けられる環境を整えることで、子どもたちが「学びをあきらめなくていい」選択肢を持てるよう配慮しています。
さらに、学習支援だけでなく、海外の学生とのオンライン国際交流イベントなど、子どもたちが“社会とつながる”きっかけづくりにも力を入れています。学校という枠にとらわれず、地域全体で子どもたちの学びを支える姿勢がうかがえる好事例です。

放課後の居場所を地域でつくる|部活動の地域移行
教育格差の背景には、学習環境だけでなく、「放課後の過ごし方」の違いも関係しています。とくに、経済的に余裕のない家庭や支援が手薄な地域では、子どもたちが安心して過ごせる“居場所”が不足しており、そのことが孤立や学習意欲の低下につながるケースもあります。
奈良市では、NPO法人こどもゆめひろばが中心となり、学校の外で地域と連携した部活動を行う「部活動の地域移行」の取り組みを進めています。具体的には、吹奏楽部のプレ練習会を市内の複数地域で開催し、子どもたちに“地域で音楽を続ける場”を提供しています。
この取り組みのポイントは、部活動という形を借りながら、誰でも参加できる“学びとつながりの場”を地域にひらくことです。学校に通っていない子どもでも、地域の活動に参加することで、新たな居場所や自己表現の機会を得ることができます。

教育格差解消は“社会全体で支える”時代へ
教育格差の問題は、特定の家庭や地域だけの課題ではありません。どこに生まれ育ったとしても、すべての子どもたちが等しく学ぶ機会を得られる社会をつくることは、未来の地域や社会を健やかに育てるために不可欠な視点です。
今回紹介したように、企業やNPOが教育現場と連携し、学費支援や体験提供、ICT環境の整備、放課後の居場所づくりなど、多様な形で教育格差の解消に取り組む動きが各地で始まっています。こうした取り組みの多くは、小さなアクションかもしれませんが、確実に子どもたちの可能性を広げるきっかけになっています。
教育は、社会の基盤であり未来そのものです。だからこそ、学校や自治体だけでなく、企業も“未来の当事者”としてこの課題に関わっていくことが、これからの時代にますます求められていくのではないでしょうか。